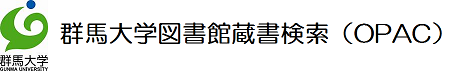※一部利用できない機能があります
| 1.
論文 |
李, 範 爽 ; 酒井, 保治郎 ; 荒木, 祐美 ; 勝山, しおり ; 田中, 志保 ; 椎原, 康史 ; 永松, 一真
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />脳磁図を用いて選択的注意課題を行う時の視覚脳活動を測定した。被検者に2種類の色\nと形からなる4つの刺激を提示し,色と形の識別による
…
ボタン押しを指示した。誘発磁場波形\nとボタン押しの反応時間を記録し,課題間比較を行った。その結果,全ての課題において刺激\n提示後100msと370ms付近で後頭葉の磁場活動が記録され,ダイポールとして第一次視覚野が\n推定された。また,ボタン押しの反応時間は350ms付近であった。ボタン押し後も後頭葉の活\n動が出現することが示唆された。
続きを見る
|
|||
| 2.
論文 |
勝山, しおり ; 石田, 純一 ; 酒井, 保治郎
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />半側空間無視の発症のメカニズムとして,注意障害説,表象障害説などがあるが,その\n本態は不明である。今回,パソコンを利用することによ
…
り,定量化,統一化が可能となり,か\nつ半側空間無視の病態解明に応用できるのではないかと考え,基礎検討を行った。従来,使用\nされてきた線分二等分試験と等価なタッチパネルによる線分二等分試験法をVisual Basicで作\n成した。健常者39名を対象に両者を比較検討し,本法は従来法と比して,同等以上の信頼性が\nあることが確認された(p<0.05)。また線分上でマーカーを動かし中央を視覚認知させるプ\nログラム,マーカーを左端で点滅させ,注意を向けるプログラムも作成したので,半側空間無\n視の患者を対象に評価ならびに治療効果の判定などに応用していきたい。
続きを見る
|
|||
| 3.
論文 |
酒井, 保治郎 ; 椎原, 康史 ; 山口, 晴保
概要:
application/pdf<br />Journal Article
|
|||
| 4.
論文 |
椎原, 康史 ; 梅沢, 章夫 ; 上玉利, 徳和 ; 宮崎, 順史 ; 酒井, 保治郎 ; 児玉, 昌久
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />現有の携帯型皮膚電位記録システムに,新規に設計した皮膚コンダクタンス(skin conductance change, SCC)の小
…
型計測deviceを接続して,24時間までの長時間SCC携帯記録を試みた。得られたSCC長時間記録の基礎的特性を同時記録した皮膚電位(skin potential activity, SPA)と比較した。活動時SCC記録は体動によるアーティファクトに安定であった。その最高値は被験者の精神性発汗の程度により変動し,発汗の強い被験者では50-60μ Siemensにも達した。一方睡眠時のSCCレベルは被験者によらず0-3μ Siemensと一定しており,途中覚醒には鋭いpeakを伴っていた。なお途中覚醒後の一過性のSPA低下はSCCでは認められなかった。これらの所見はSCCが覚醒水準の定量的分析に有利な指標であることを支持する。またうつ病患者の不眠でしばしば観察された睡眠時SPAのレベル上昇が,SCCにおいてもSPAと同期して出現したことから,その原因はSPA参照部位の電位変動によるものではなく,実際に交感神経優位の状態が出現するためであることが確認された。
続きを見る
|
|||
| 5.
論文 |
酒井, 保治郎 ; 都丸, 正 ; 山口, 晴保 ; 岡本, 一真
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />オドボール課題としてよく使用される選択反応時間課題では,事象関連電位測定時の波形に運動関連脳電位が重畳していることをそれぞれを同時に
…
測定することにより明らかにした。この重畳する運動関連脳電位の事象関連電位への影響を検討するためのシミュレーションプログラムを開発した。その結果,運動関連脳電位の重畳がP300振幅を小さくすること(通常5~6mVの減少),ならびにP300潜時にも最大数ms程度の影響を及ぼすことがわかった。本プログラムは選択反応時間課題で測定した事象関連電位において,運動関連脳電位の影響を調べるのに有効であった。
続きを見る
|
|||
| 6.
論文 |
岡本, 一真 ; 酒井, 保治郎
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />群馬県立循環器病センターに群馬大学神経内科より派遣された医師が担当した入院患者のうち,急性期脳梗塞・脳出血患者(以下急性期CVD患者
…
)と神経学的に異常ない患者(以下非神経疾患患者)の退院先を,リハビリテーション(以下リハビリ)施行の有無と合わせて検討した。対象は1992年6月より98年5月までの全患者943例中,急性期CVD患者285例(脳梗塞235例,脳出血50例)と非神経疾患患者192例とした。死亡例や神経内科以外の疾患治療のため転院した症例を除くと,自宅退院の割合は,急性期CVD患者が非神経疾患患者より有意に低かった。急性期CVD患者について,自宅退院と自宅以外への退院を比較したところ,主病変が脳の左右いずれにあるかは退院先に影響せず,高血圧,不整脈,糖尿病,高脂血症,狭心症,心筋梗塞などの心疾患合併は,自宅退院を阻害する因子ではなかった。またリハビリ施行例は,リハビリ非施行例よりも自宅退院の割合が高い傾向があったが,有意差はなかった。今回調べ得た中では,麻痺や痴呆などによる介護が必要なことが,自宅退院の妨げになると思われた。急性期CVD患者では発症年齢が高くなるにつれて痴呆や麻痺による介護が必要な患者の発生率が上昇した。そしてこれらの患者が自宅に退院する割合は,高齢になるに従って低下する傾向があった。このような介護が必要な患者が自宅に帰るには,介護可能な家族の存在が不可欠である。患者と配偶者の高齢化,少子化が進行する中,要介護患者を社会が支えていくには,家族の対応のみでは不十分で,公的なサービスの充実が望まれる。
続きを見る
|
|||
| 7.
論文 |
小板橋, 喜久代 ; 柳, 奈津子 ; 酒井, 保治郎 ; 菱沼, 典子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />漸進的筋弛緩法によるリラクセーションの効果を検証する目的で,安静法(対照実験)と漸進的筋弛緩法(Progressive Muscle
…
Relaxation Method以下PMR法と略)時における,脳波および心拍変動解析を行った。あわせてSTAI不安テストと身体感覚尺度を用いて認知・感覚的反応を評価した。対象は,健康な女性6名である。データは,同一被験者に日を替えて3回測定した。1日目は実験室及び実験条件に慣れるための予備日とし,2日目と3日目に安静法とPMR法を体験させて,両データを比較検討した。その結果,(1)脳波の高速フーリエ変換(FFT法)による分析が可能であった4例中の3例について,α波およびθ波の周波数帯域のPower値を比較したところ,安静法時には僅かな増加傾向が示され,PMR法時には顕著な増加が見られた。(2)平均心拍数(HR)および平均RR間隔は,6例中5例において,PMR法時に,HRの減少と平均RR間隔の延長が見られた。1例はPMR法時にHRの増加を示し,平均RR間隔の短縮を示した。なお,CV_<rr>値(心拍変動係数)と,FFT解析による高周波数帯域・低周波数帯域の割合については,対照実験との差は明らかにされなかった。(3)全例においてSTAI状態不安得点の低下と筋弛緩感覚の高まりを示す身体感覚尺度得点の上昇が見られ,PMR法時に顕著であった。
続きを見る
|
|||
| 8.
論文 |
酒井, 保治郎 ; 山口, 晴保 ; 中村, 多美子 ; 桜井, 篤志 ; 平井, 俊策
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />脳血管障害,脳炎などの脳の局所病変で入院した220症例を対象に,motor impersistence (MI)の有無を調べた。MI
…
は9例で陽性であったが,すべて脳梗塞の症例であった。これは全体の約4.1%,脳血管障害の約5.6%に相当した。外来のMI陽性の脳出血後遺症の1症例を加え,10症例のMRI画像からMIの責任病巣を検討した。その結果,責任病巣は劣位半球のBrodmannの第6,8野の中で,中大脳動脈の潅流域で,しかも前大脳動脈潅流域に近い領域の皮質ないし皮質下白質であったが,主体は皮質下白質と考えられた。MIの発現にはこの部位での神経線維のdisconnectionが関与している可能性が示された。
続きを見る
|
|||
| 9.
論文 |
岡本, 一真 ; 酒井, 保治郎 ; 岡本, 幸市
概要:
application/pdf<br />Journal Article
|
|||
| 10.
論文 |
山口, 晴保 ; 鳥屋, 幸子 ; 大森, 庸子 ; 清水, 一 ; 吉川, ひろみ ; 小林, 夏子 ; 加固, 正子 ; 酒井, 保治郎 ; 茂原, 重雄 ; 中澤, 次夫
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />We have examined the mental function and activity of daily living (ADL) in the Haruna-Ikoinosono Nursing Home 3 times: 6 years ago, 3 years ago and this year. Only 38 persons of
…
original 131 remain in the nursing home. They were divided into 3 groups: 1) 16 persons with low ADL levels at the 1st examination (ADL-Low group); 2) 8 persons without loss of ADL (ADL-Keep grpup); and 3) 14 persons with marked loss of ADL (ADL-Down group). The most prominent difference between ADL-Keep and ADL-Down group was age; mean age of 80.5 in the ADL-Keep group was significantly younger than that of 87.7 in the ADL-Down group. The mental function was declined more markedly in ADL-Low and ADL-Down groups than in ADL-Keep group. It suggests that decreased ADL promotes a loss of mental function.
続きを見る
|