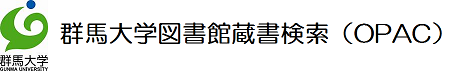※一部利用できない機能があります
| 1.
論文 |
田邉, 美佐子 ; 吉田, 久美子 ; 黒澤, やよい ; 神田, 清子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【目的】 小児期に骨髄ドナーになったきょうだいの経験を記述し, 小児ドナー経験者への看護支援を検討する. 【対象と方法】8歳の時に6歳の妹に骨髄提供をした2
…
0代前半の女性A氏に面接を行い, 質的記述的に分析した. 【結果】A氏は骨髄提供について, 躊躇する気持ちや親の期待を感じながらも, 自分の意思で決めたと認識していた. 骨髄提供後は, 妹との一体感を感じるようになり, 妹を見守ってきた. 現在は, ドナーになってよかった, 自慢できることだと捉えていた. 【結語】小児ドナー経験者は, 現在の状況からドナーになった理由を捉え直すこと, レシピエントのQOLが自己価値観に影響を及ぼすことが示唆された. 思春期・青年期に歪んだ自己存在が認知されないよう, 継続した直接的支援とレシピエントを介した間接的支援の必要性が考えられた.
続きを見る
|
|||
| 2.
論文 |
青木, 君恵 ; 田邉, 美佐子 ; 神田, 清子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,1998年1月から2008年6月までに掲載された病を抱える患者の生き\n方・生きる意味に関する論文を分析し,看護研究
…
の動向と課題を明らかにすることである。医\n学中央雑誌を用いて「生き方」「生きる意味」「人生観」と患者,看護をキーワードに検索を行い,\n研究デザイン,方法,内容の分析を行った。その結果,対象論文は60件であり,研究デザイン\nは因子探索研究が83.3%,種類は質的研究が93.3%を占めていた。研究内容は,《1.病や治\n療体験を通した生き方》《2.病や治療を通して患者が体験し,生き方を模索するプロセス》\n《3.患者の生き方と看護の効果・示唆》《4.病と生き方の関連性》の4つのカテゴリが形\n成された。病を抱える患者は,過去と現在の自分を振り返る中で,自己と対峙し自己成長しな\nがら未来に向かって生きていることが明らかにされた。生き方の意味づけを促進するためには\n患者の体験に寄り添った傾聴をはじめとする看護支援が重要であることが示唆された。
続きを見る
|
|||
| 3.
論文 |
田邉, 美佐子 ; 青木, 君恵 ; 神田, 清子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,造血幹細胞移植後に再発し,その後,長期寛解状態となった子どもを\n養育している母親の認識を明らかにし,看護支援を検討
…
することである。長期寛解を維持して\nいる子どもを持ち,同意が得られた母親3名に半構成的面接を実施した。子どもが発病してか\nら現在までの経過とその期間に感じたこと,現在の子どもへの関わりと思いを中心に自由に語\nってもらい,ストーリーを記述する方法による質的記述的分析を行った。\n養育上の認識は,1)子どもが生きている,普通に生活できているだけで充分である,2)\n先のことは考えずに,今,何をすべきかが大切である,3)子どもの笑顔を引き出そうとする,\n4)新たな困難が訪れても受け入れて乗り越える,の4つが見出された。これらの思いや姿勢\nの根底には,子ども喪失への危機感を抱いていることが考えられた。\n看護者は母親の思いを理解したうえで,母親が子どもにしてあげたいと思うことを支えてい\nくとともに,子どもの成長に応じた養育ができるような援助を行う必要がある。
続きを見る
|
|||
| 4.
論文 |
田邉, 美佐子 ; 瀬山, 留加 ; 神田, 清子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【背景・目的】小児がん経験者の子どもを持つ両親の語りから夫婦および家族における療養生活構築のプロ\nセスを理解し, 看護への示唆を得る. 【対象と方法】発病
…
から5年を経過した小児がん経験者Aちゃんの\n両親それぞれの語りを当事者の視点でストーリーを記述し, 出来事の意味を解釈した. 【結果】父親と母\n親は, 共通の目標を持って子どもの病気と向かい合い, 祖父母の多大な支援を受けて家族が親密性を高めな\nがら療養生活を構築していた. 子どもの病気を乗り越えた父親, 母親は共通して自己成長を自覚し, 人生にお\nいて子どもの病気が必要な出来事であったと肯定的に意味づけていた. 【結語】小児がん患者の家族が\n安定した療養生活を構築していくためには, 父親と母親が支えあう関係を維持できるような援助と, 効果的\nなソーシャルサポートが活用できるような援助が必要であることが示唆された.
続きを見る
|
|||
| 5.
論文 |
瀬山, 留加 ; 吉田, 久美子 ; 田邉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,手術不適応,あるいは転移やがんの増悪を診断され,化学療法を開始\nした消化器がん患者が,副作用や期待する治療効果が得
…
られなくとも化学療法を受ける意思決\n定を行った要因について明らかにし,必要な看護支援の検討を行なうことであった。\n対象者10名に対し半構成的面接法によるデータ収集を行い,質的分析を行った結果,64のコ\nードから18のサブカテゴリー,4のカテゴリーが形成された。\n明らかとなった意思決定要因のうち,≪がん治療に対する認識≫≪ソーシャルサポート≫≪\n建設的な志向≫は,自己の内生を源としているため,それらに基づく意思決定は自発的であっ\nたと考えられた。一方で,≪自分の力だけでは変えられない境遇≫はジレンマを抱えた状況で\nあり,自己効力感や希望の喪失が生じていたことから,自発的な意思決定行為を弱化させてい\nたと推察された。\n化学療法を受ける患者は,治療が一回で完結するものではないため,意思決定機会が何度と\nなく訪れていた。患者が自発的な意思決定を継続的に行うためには,そのプロセスに寄り添い\nながらも,結論に至った自己決定を肯定的に評価し得る前向きな要因を成立させる看護介入の\n必要性が示唆された。
続きを見る
|