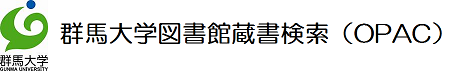※一部利用できない機能があります
| 1.
論文 |
Minamitani, Akimasa ; 南谷, 覺正
概要:
Departmental Bulletin Paper<br />This essay is an attempt to organize a perspective for education as a form of communication through which information, the vital components of the mind, is imparted to students. Since the modern
…
society seems to be at the end of its tether with nature endangered, war and conflict perpetual, and the way out still unseen, it is necessary to create a new concept of civilization with which to transcend the modern and incorporate awareness of that concept in education.
続きを見る
|
|||
| 2.
論文 |
ヤマグチ, アキヒロ ; オトヤマ, ワカホ ; Yamaguchi, Akihiro ; Otoyama, Wakaho ; 山口, 陽弘 ; 音山, 若穂
概要:
Departmental Bulletin Paper
|
|||
| 3.
論文 |
オトヤマ, ワカホ ; ヤマグチ, アキヒロ ; Otoyama, Wakaho ; Yamaguchi, Akihiro ; 音山, 若穂 ; 山口, 陽弘
概要:
Departmental Bulletin Paper
|
|||
| 4.
論文 |
タカハシ, ノゾム ; Takahashi, Nozomu ; 高橋, 望
概要:
Departmental Bulletin Paper
|
|||
| 5.
論文 |
大桃, 道幸
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />Thomas Hardy の最後に出版された小説 The Well-Beloved は、England の辺境The\nIs
…
le of Slingers を舞台に、彫刻家Jocelyn Pierston が島の娘Avice Caro,その娘、孫娘と三代\nに渡って同名の女性を愛するという,Hardy の後期の小説としてはかなり異質の作品である。\n物語の非現実性と外界から隔絶したような島の特異性から,この作品は一種のファンタジーと\nして,捉えることのできない理想の女性を追い求める男性の物語,プラトニックなイデアの追\n求をテーマとする作品として読まれることが多い。しかし,一見ファンタジーのような体裁を\n取りながら,The Well-Beloved にはHardy の後期の小説に通底する社会史的な側面があり,\nそれは時代の潮流と伝統的な島,つまり新旧の対立という問題である。鉄道と教育に象徴され\nる近代化によって,古来ほとんど変化のなかった島も変化を余儀なくされる。Avice Caro の\n死は古き島の消滅を表すメタファーであり,主人公Pierston がAvice 二世,Avice 三世に寄\nせる想いは,亡きAvice Caro そして彼女の精髄であるかつての島に寄せる想いなのである。
続きを見る
|
|||
| 6.
論文 |
村田, 祥子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />現代社会は政治,経済,文化のさまざまな面で急激な変化をしている。人びとは教育が\nあらゆる問題を解決すると信じており,教育の果たす役
…
割はより重要になりつつある。本論は\n大学生の教育の捉え方について報告する。自由連想課題を用いた。被験者は刺激語を提示され,\n有意味な連想した関連語をあげるように求められた。知識はネットワーク構造に組織化されて\n貯蔵されており,そこでは単語や概念がその他の概念と連想経路を介して結びついているとさ\nれている。反応語は「教育」という語の語彙連想ネットワークマップを作成するのに利用した。\n連想語マップは語の重要な属性を捉える。結果は,「教育」と「学校」「先生」とが連想関係に\nあることを示した。被験者たちは,学校を教育の重要な場所のひとつと考えていた。彼らは学\n力低下といじめ,不登校のような生徒の問題行動に関心を示した。
続きを見る
|
|||
| 7.
論文 |
大桃, 道幸
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />Thomas Hardyが小説家としての円熟期に書いた短編小説The Son's Vetoは,村の牧師Twycott氏と結婚した田舎
…
娘Sophyの悲劇的な人生を描いた作品であり,中心テーマは階級(意識)である。Sophyの結婚は彼女自身の階級意識によって規定され,Twycott氏の死後,彼女の人生は息子のRandolphの階級意識によって支配される。Randolphは階級意識が強く,自分の出世しか念頭にない偏狭な人間である。Hardyは彼の人物像を過不足なく描き,彼を非難することで,このような人間性に欠けるエリートを育てるパブリックスクールや大学の教育を糾弾している。また,The Son's Vetoには,階級の問題と絡み合う形で,農村と都会の対立というテーマが織り込まれていて,Sophyとその息子との対立は農村と都会との対立であるとも理解できる。Hardyの長編小説では,主人公が外の社会に出て行くことにより,階級という障壁にぶつかり,希望をくじかれるというパターンが一般的である。しかし,The Son's Vetoでは階級の壁が家族の中にまで侵入しているのが特徴で,階級の問題がより深刻化していることを示すものであり,Hardyの危機感の現れと思われる。
続きを見る
|
|||
| 8.
論文 |
内田, 陽子 ; 新井, 明子 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は群馬大学医学部保健学科での老年看護学実習の評価を行い,学生の高齢者に対する看護実践のやる気を高める条件を明らかにするこ
…
とである。対象は2004年5月から7月にかけてS介護老人保健施設で実習をした39人の本大学の学生である。調査は学生の実習終了最終日に学生に質問紙を配布し,各自記入をしてもらった。質問紙の主な調査項目は,(1)学生の高齢者看護実践のやる気の程度と,それに影響する条件として(2)学生の背景条件,(3)受け持ち高齢者の背景条件,(4)実習における学習の程度に関する項目を設定した。結果,1,学生にとって受け持ち高齢者へのアセスメントや看護実践に対しては教員が,他の高齢者に対する看護実践では看護師が有効であると認識していた。 2,学生の看護過程や技術に対しての自己評価は高かった。3,痴呆棟に実習に行った学生のほうが,高齢者から拒否された経験が生かされ関わる自信がついていた。4,学生の今後の高齢者に対する看護実践のやる気と有意な正の相関がみられた項目は,「アセスメントができた」,「実習が楽しかった」,「介護老人保健施設に就職したい」,「元来実習が好きである」,「受け持ち高齢者に拒否された経験があった」,「受け持ち高齢者に対する看護技術の実践」であった。「受け持ち高齢者の排泄が自立している」については負の相関がみられた。5,学生のやる気はグループ毎に相違があり,最も有効なやる気を高める条件は「実習が楽しかった」であった。痴呆高齢者に拒否されても,日々のケアのなかで患者と分かり合えることを促す指導を実践していくことが求められる。教員は授業としての実習を展開するなかで,学生の気持ちや表情を観察し,学生が問題解決のどの過程にあるか,満足いく実習ができているか常に確認していく必要がある。
続きを見る
|
|||
| 9.
論文 |
大桃, 道幸
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />英国の小説家・詩人Thomas Hardyの短編小説The Melancholy Hussar of the German Legi
…
onはナポレオン戦争時代を背景に,イングランド南部丘陵地帯にやって来たドイツ騎兵部隊の一兵士とその地に住む娘との悲恋を描いた作品である。この作品は良く知られてはいるものの,ほとんど研究されておらず,単なるメロドラマに過ぎないといった低い評価を受けたりもしてきた。しかし,丁寧に読んでみると,この作品にはHardyがよく取り上げている人間の孤独,女性と結婚,愛と義務,更には上流階級批判といった重要な要素が巧みに織り込まれていて, Hardyの文学を理解する上で見落とせない作品となっている。また全体としては,女主人公Phyllisに共感する語り手によって語られる物語にノスタルジックな雰囲気が漂い,読後の余韻も深く,読者に忘れがたい印象を残す作品に仕上がっている。本作品は,小説家として円熟期にあったHardyの力量を随所に感じさせる優れた作品であると言って良いだろう。
続きを見る
|
|||
| 10.
論文 |
大桃, 道幸
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />トマス・ハーディの短編小説To Please His Wifeは, 野心のために夫と二人の息子を失った女性ジョアンナの半生を描いた作
…
品である。ハーディの短編小説は長編小説に比べ, 過小評価されてきた嫌いがあり, To Please His Wifeもまたその例に漏れず, 因果応報, 自業自得の単純な物語として片付けられがちである。しかしながら, 小説家ハーディの円熟期に書かれたこの作品はその簡潔なペーソスあふれる筋立ての中に, 結婚, 階級(意識), 野心, 教育, 出世といった同時期に書かれた長編小説に共通するテーマが織り込まれていて, ハーディ文学を理解する上で見落とせない作品となっている。ハーディはまた, 主人公のジョアンナを野心のために身を滅ぼした一人の愚かな女性から〈船乗りの妻〉という普遍的な悲劇のヒロインへと高めることにより, To Please His Wifeを時空を超えた感動的な悲劇的作品にしている。
続きを見る
|