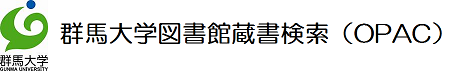※一部利用できない機能があります
| 1.
論文 |
Koike, Ayano ; Uchida, Yoko ; 小池, 彩乃 ; 内田, 陽子
概要:
Journal Article
|
|||
| 2.
論文 |
Tajima, Reiko ; Koyama, Akiko ; Uchida, Yoko ; 田島, 玲子 ; 小山, 晶子 ; 内田, 陽子
概要:
Journal Article<br />【目 的】本研究の目的は,一般住民を対象とした研修会の参加者が在宅サービスに対してどのような期待を持ったのか,また,その期待は,人生の最期を過ごしたい場所による違いがあるのかを明らかにすることである
…
. 【方 法】対象者は,地域包括ケアに関する一般住民を対象とした研修会に参加し,調査に同意し,有効回答を得た265名.調査は,背景と在宅サービスへの期待度を問う自記式質問紙とした.分析方法は,自宅選択者群と非自宅選択者群に分けてχ2検定,Mann-WhitneyのU検定を用いた. 【結 果】在宅サービス期待度平均値は3.4以上と期待する側に寄っている中,「緊急時連絡先提示」,「家族の介護負担軽減」は3.77と最高値であった.自宅選択者は非自宅選択者に比べ,「精神的安定」,「入院回避」,「希望サービスの利用」,「利用回数や時間の希望」の期待の程度が高かった. 【結 論】研修会に参加した一般住民の在宅サービスへの期待が高い中,自宅選択者と非自宅選択者では,4項目で違いが示された.
続きを見る
|
|||
| 3.
論文 |
Koike, Ayano ; Uchida, Yoko ; Suzuki, Mineko ; Tsuganezawa, Rieko ; 小池, 彩乃 ; 内田, 陽子 ; 鈴木, 峰子 ; 津金澤, 理恵子
概要:
Journal Article<br />【目 的】 認知症の行動・心理症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia: BPSD)が重度の患者を対象に包括的BPSDケアシステム®(
…
以下システム)を実施し,その有効性を評価する. 【対象と方法】 対象者は急性期治療を担うC病院の入院患者であり,認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上,NPI-Qが10点以上,研究の同意を得た10名とした.対象者にシステムを実施した.評価は入院時,介入後1・3・5週間の時点で行った.BPSDはNPI-Qで評価を行った. 【結 果】 対象者10名の入院時NPI-Q重症度得点は13.5±2.1点から入院1週間後は8.7±5.6点と有意に改善した(p=0.027).10名中7名が3週間以内に退院,転院できた. 【結 語】 重度のBPSDをもつ患者には,包括的BPSDケアシステム®における個別アクションプランが必要であることが示唆された.
続きを見る
|
|||
| 4.
論文 |
Nashiki, Emiko ; Uchida, Yoko ; Saitoh, Takayuki ; 梨木, 恵実子 ; 内田, 陽子 ; 齋藤, 貴之
概要:
Journal Article<br />【目 的】 群馬県の訪問看護ステーション(以下,ステーション)における COPD 患者の背景とアクションプラン(AP)導入状況を明らかにする. 【方 法】 調査方法はステーション 187 施設への無
…
記名自記式質問紙調査(郵送法).回答はステーション管理者が調査時の状況を記載した. 【結 果】 返信は 79 施設(回収率 42.2%).COPD 患者のいるステーションは 45 施設(57.0%).患者は,全員が 65 歳以上,8 割が介助を必要とした.AP を有する患者のいるステーションは 20 施設.AP の内容は様々だった.AP を有する患者ケアの実施得点は,AP のない患者に比べ「吸入薬がある場合は吸入指導」,「増悪した時の対応の教育」が高かった(p<0.05).また COPD 患者のいるステーションは,いない所と比べ「常勤看護職員数」と「総患者数」が有意に多く(p<0.01),「24 時間対応体制加算」も多かった(p<0.05). 【結 語】COPD 患者が地域での暮らしを続けるには,ステーションの患者の個別性に配慮した AP 作成が必要である.
続きを見る
|
|||
| 5.
論文 |
内田, 陽子
概要:
Journal Article
|
|||
| 6.
論文 |
小池, 彩乃 ; 内田, 陽子 ; 齊田, 綾子
概要:
Journal Article
|
|||
| 7.
論文 |
田島, 玲子 ; 佐藤, 文美 ; 内田, 陽子
概要:
Journal Article
|
|||
| 8.
論文 |
鈴木, 峰子 ; 佐藤, 文美 ; 福田, 未来 ; 内田, 陽子
概要:
Journal Article
|
|||
| 9.
論文 |
内田, 陽子 ; 井出, 成美 ; 桐生, 育恵 ; 松井, 理恵 ; 亀ヶ谷, 忠彦 ; 吉田, 亨 ; 小山, 晶子 ; 上山, 真美 ; 横山, 知行 ; 佐藤, 由美
概要:
Journal Article
|
|||
| 10.
論文 |
小板橋, 梨香 ; 内田, 陽子 ; 河端, 裕美
概要:
Journal Article
|
|||
| 11.
論文 |
安藤, 亮 ; 内田, 陽子
概要:
Journal Article<br />目的:本研究の目的は, 地域に在住する高齢者の閉じこもりの有無と背景条件による興味のある活動の違いについて明らかにすることである.対象と方法:対象者はA 市のB地区における65歳以上の高齢者240名
…
のうち, 本研究に対する同意を得られた者42名である.研究者が調査票に沿って訪問聴き取り調査を行った.JICE 得点について背景条件(日常生活自立度,世帯構成,移動手段) のそれぞれの項目内及び閉じこもりの有無により2群に分け, 2群間の比較をMann-WhitneyのU 検定を用いて行った.結果:外出頻度より閉じこもりあり群12名(うち閉じこもり4名,閉じこもり予備群8名),閉じこもりなし群は30名であった.閉じこもり有無別にJICE 得点を比較した結果,閉じこもり群の方が非閉じこもり群よりも「ドライブ」,「異性との付き合い」,「ラジオ」の項目において得点が低く, 有意差を認めた(p<0.05).結語:閉じこもりの有無及び自立度, 世帯構成, 移動手段により興味のある活動に違いがあった. 閉じこもりを含めた地域在住高齢者への介護予防支援については, 高齢者の興味のある活動を取り入れ, 身近な場所で社会との交流が保てるようなプログラムを高齢者と共に作成・実施し, 効果の検証を行うことが必要であると考えられる.
続きを見る
|
|||
| 12.
論文 |
Uchida, Yoko ; 内田, 陽子
概要:
Journal Article<br />Objectiye: To validate the Outcome and Assessment Scale for Dementia Care (OASDC) by comparison\nwith the Multidimensional Observation Scale for Elderly Subjects (MOSES). Methods: The targets\nwere 126 Jap anese nurses,
…
together with 126 of their demented patients. The self- administered question-\nnaire asked the nurses about the condition of their patients. The questionnaire consisted of 20 OASDC\nitems, including the base attributes of the nurses and their patients, and 40 MOSES items. OASDC was\nsubjected to a factor analysis and the correlations between OASDC and MOSES were explored.\nResults: The factor analysis revealed that OASDC had 5 factors : Self-care; Tranquility; Social role;\nBehavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD),; and Caregiver and the cumulative\ncontribution ratio of all five factors was 63.196. There was a significant correlation between OASDC\nand MOSES except for the items of care factors (r=O.201 to O.926, p<O.05). Conclusion : The evalua-\ntion almost completely secured the validity of the construct validity and contemporary validity of the\nOASDC.
続きを見る
|
|||
| 13.
論文 |
川久保, 悦子 ; 内田, 陽子 ; 小泉, 美佐子
概要:
Journal Article<br />[目 的]認知症高齢者に対して「絵画療法プラン」を作成,実践し,(1)絵画療法が認知症高齢者にもたら\nす効果,(2)認知症高齢者の作品の特徴,(3)肯定的反応および否定的反応を示した絵画療法の画題
…
,(4)絵画\n療法を効果的に進めるための介入方法を明らかにした.[対象・方法]対象者は,認知症をもつ年齢65歳以\n上の高齢者で,認知症グループホームHを利用し,調査協力を得た5名である.3か月間に,週1回,60分程度\nの「絵画療法プラン」を計12回介入した.評価は内田1の認知症ケアのアウトカム評価票,BEHAVE-ADを\n使用し,各回の絵画作品の評価も行った.また対象者の反応をカテゴリー分類した.[結 果]対象者5名\nすべて女性であり,年齢は86±5.9歳(平均±SD),全員がアルツハイマー病であった.(1)絵画療法が認知症\n高齢者にもたらす効果は「周辺症状」,「介護ストレス・疲労の様子」,「趣味・生きがいの実現」,「役割発揮の\n有無」の改善と,「制作への自主性」や「他人の作品を褒める」などの肯定的な行動や言動をもたらした.(2)\n作品は色あざやかで抽象度が高く大胆な構図で,単純化などの特徴がみられた.(3)認知症高齢者に肯定的な\n反応であった画題は「色彩が原色で彩度が高く,工程が単純,写実ではなく自由表現をいかした画題」「昔使っ\nていた材料を使った画題」「生活の中で役に立ち,手芸を取り入れた画題」「色や素材を選択できる画題」で\nあった.(4)絵画療法には肯定的な言動の反面「できない」という,相反する感情もあった.[結 語]絵画\n療法は,認知症高齢者の精神活動によい効果をもたらすが,ケア提供者が絵画療法プランを取り入れること\nで,認知症高齢者のいきいきとした反応や言動を発見することができる.介入により新たに発見したことを\nアセスメントし,認知症高齢者ができることを促すようなケアを行うことが求められる.落ち着いた環境を\n整え,画題と介入方法を考慮する必要がある.
続きを見る
|
|||
| 14.
論文 |
内田, 陽子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />本研究の目的は, 地域住民に対して, 尿失禁予防・対処活動を継続するためのカレンダー表を配布し, その記載と活動の実施状況, その評価を明らかにすることであ
…
る. 対象はA市開催の介護予防講座の尿失禁予防講演会に参加した住民100人とした. 方法は, 第一段階として, 講演会参加者に対して骨盤底筋体操, 水分摂取の工夫, 便秘予防の3カ条を1ヶ月間実践してもらうカレンダー表を渡し, 郵送返信してもらった. つぎに, 第二段階として, 第一段階のカレンダー返信者に対して, 骨盤底筋体操実施の有無だけを記載する3ヶ月間のカレンダーを郵送した. 結果, 第一段階での返信者は 20人であり, 1ヶ月間(30日間)3カ条すべてを実施した日数の割合は30日間の61.8±29.8%を占めた. また, 排尿症状をもつ者でそれが改善した者が4人いた. 第二段階での返信者は10人であり, 3ヶ月間における実施した日数の割合は90日間の78.7±17.0%であり, 排尿症状をもつ者での改善者は5人いた. 以上のことから, 予防活動継続のためには目的と活動の項目を絞ったカレンダー表の戦略が有効である.
続きを見る
|
|||
| 15.
論文 |
内田, 陽子 ; 河端, 裕美
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />本研究の目的は神経難病患者に対して訪問看護のアウトカム評価を明らかにすることである. 対象はA脳・神経疾患の専門病院併設のB訪問看護ステーションでケアを受け
…
ている神経難病をもつ利用者7名である. アウトカム評価の方法は日本版在宅ケアのアウトカム評価表及びSEIQoL-DWのQoLの測定方法を用いて, 訪問看護での3ヵ月前後の変化を測定した. その結果, QoLが最高値持続, 改善した事例は5事例であり, 訪問看護師によるアウトカム評価においても改善,悪化傾向が同じ数の傾向にあった. QoL が低下している事例は2事例であり, アウトカム評価においても悪化傾向が多かった. よって, 訪問看護師は徐々に悪化していく神経難病患者に対しても改善傾向に着目し, アウトカム評価に対する働きがけが必要である.
続きを見る
|
|||
| 16.
論文 |
内田, 陽子 ; 内田, 真理子 ; 町田, 沙紀子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は地域住民ができる認知症予防法に関連する因子を明らかにし,地域住民\nへの認知症予防における看護職の役割と効率的な認知症
…
予防法の戦略について検討することで\nある。対象はA市の住民で,市が発行する広報誌に掲載されていた認知症予防講習会の案内を\nみて講習会に参加し,調査の協力を得た196人である。方法は自記式質問紙法で,主な調査項\n目は住民の属性,自分ができる認知症予防法,脳の健康度チェック表である。結果,A市の住\n民ができる認知症予防法は「新聞を読む」,「野菜をとる」が上位にあがった。脳の健康度チェ\nック表では,独居,通院者,65歳以上の者の危険に該当する項目数が有意に多かった。ロジス\nティック回帰分析の結果,非危険群において「旅行ができる」,「65歳未満」が有意な因子であ\nった。これらの属性をふまえて,住民の介護予防戦略を考えていく必要がある。
続きを見る
|
|||
| 17.
論文 |
上山, 真美 ; 内田, 陽子 ; 小林, 千鶴
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,介護支援専門員をはじめとする支援者に対して行った,高齢者の排尿\nケアに関する学習会の評価と介護支援専門員が困難と感
…
じた事例の課題を明らかにすることで\nある。対象は,A地区の排尿ケアに関する学習会に参加し,協力の得られた50名とした。方法\nは,自記式質問紙法とした。結果,職種にかかわらず,約75%の者が,排尿ケアに関して困難\nと感じた課題を持っていた。学習会の内容については,約90%の者が役に立つと回答していた。\n一方,排尿日誌において学習した内容を実践してみようと思うと回答した者の得点は,役立つ\nと回答した者の得点に比べて低く有意な差がみられた(p=0.003)。また,全体で多かった課題\nは,「尿失禁の具体的ケア方法」,「受診を勧める時期」,「尿失禁のタイプ診断」であった。一方,\n介護支援専門員がその他の職種に比べて有意に高かった課題は,「オムツの種類・選択」であっ\nた。以上より,対象に合わせてオムツ選択ができるフローチャートやタイプ別排尿ケアアセス\nメント方法のフローチャートを開発し,それらを活用できるようにすることが求められる。
続きを見る
|
|||
| 18.
論文 |
内田, 陽子 ; 中谷, 久恵 ; 島内, 節
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【背景・目的】介護支援専門員が判断したエンド・オブ・ライフケアニーズと在宅ケアマネジメントの実践状況を明らかにする.【対象と方法】対象はA県の現任研修を受講
…
した介護支援専門員のうち, 在宅における終末期事例を受け持ち, 調査の協力が得られた77人とした. 方法は, 終末期の各期別に介護支援専門員が関わったかどうか, また, 各期の利用したサービス, ケアマネジメントニーズの必要性判断や実践の有無等について構成されている質問紙による調査である.【結果】介護支援専門員の事例への関わった割合は小康期, 開始期, 臨死期の順で高く, ニーズの判断や実践の高かった項目は「ケア体制の確立」であった. 終末期ケアのマネジメントの困難さについては, かなり困難を感じる者が半数以上を占めた.【結語】これらについての結果は, 介護支援専門員の年齢や経験年数, 資格によって差があり, 今後, ケアマネジメントに対する質向上のための研修及びシステムの構築の必要性が明確になった.
続きを見る
|
|||
| 19.
論文 |
内田, 陽子 ; 梨木, 恵実子 ; 小玉, 幸佳 ; 河端, 裕美 ; 鈴木, 早智子 ; 高橋, 陽子 ; 斉藤, 喜恵子 ; 滝原, 典子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【背景・目的】病院スタッフからみた老人看護専門看護師臨地実習の評価を明らかにすることである. 【対\n象と方法】調査協力に同意が得られた病院スタッフ74名に
…
対して, 自記式質問紙法を行った. 【結果】\n実習生の関わりとCNSの6つの役割に対する評価は「学生のケアプランは良かった」 「スタッフに対する意\n見,アドバイスは良かった」等について高得点を示した. その他, 「根気よく関わる大切さがわかった」等のス\nタッフ自身への良い変化の回答もみられた. しかし, これらの得点は, 看護師とそれ以外のスタッフでは差が\nみられた. 【結語】学生はスタッフに実習や役割を理解してもらうことが必要であり, そのためには, 他\n職種に対する積極的な関わりが必要である.
続きを見る
|
|||
| 20.
論文 |
内田, 陽子 ; 清水, さゆり ; 杉山, 学 ; 高橋, 陽子 ; 加藤, 綾子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【目的】認知症ケアのアウトカム評価票の項目別にみた重み付け得点と影響する評価者の因子を明らかに\nすることである. 【方法】第1段階の調査ではA県で行われた
…
ケアマネジャー研修とA県看護協会の研\n修に参加した計542人を対象に評価票の大カテゴリーの重み付け得点化を行った. 第2段階の調査では, 脳\n神経疾患を専門に扱う美原記念病院とその関連施設で働く認知症経験をもつ職員22人を対象に, 大・中カテ\nゴリーに対する重み付け得点化を行った. 分析はAHP理論を活用した. 【結果】第1調査では重み付け\n得点に関連する評価者の因子は職種, 所属機関, 経験年数であった. 第2調査では背景条件との関連はみられ\nなかった. 両調査とも「その人らしい生き方」に対する得点は高かった. 【結論】これらの評価者の因子\nの調整を行い, 重み付け得点化を行う必要がある.
続きを見る
|
|||
| 21.
論文 |
岩永, 喜久子 ; 松田, たみ子 ; 内田, 陽子 ; 二渡, 玉江 ; 神田, 清子 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />群馬県における認定看護師教育のニーズを明らかにする目的で,群馬県内54施設に勤務\nする看護職2703名(回収率86.9%)を対象に
…
自記式質問紙調査を行った。認定看護師教育を希\n望するものは36.0%であり,その内,群馬大学における教育を希望するものは,87.2%(733名)\nであった。希望する認定分野は緩和ケアが最も多く,次いで救急看護,認知症看護,がん化学\n療法看護の順であった。認定看護師を希望しない理由は,「興味はあるが仕事の継続に支障を\nきたす心配がある」46.0%,「教育についていけるか不安である」39.9%,「入試に合格するか\n心配である」24.7%などであった。\n本学は認定看護師教育機関として,社会のニーズに応え,より良いがん看護の充実に向けた\n設置準備が求められている。
続きを見る
|
|||
| 22.
論文 |
内田, 陽子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は介護保険対象者でサービスにより状態が改善し自立となった利用者の特\n性を明らかにし,サービス導入の検討を行うことである
…
。対象はA県ケアマネジャー現任者研\n修受講者で調査の協力を得られ,状態が改善し自立となった在宅ケア利用者を受け持ったこと\nのあるケアマネジャー92人とした。結果,自立となった利用者は,「要支援・要介護1」の軽\n度者で,家族と同居しているものが多かった。特に効果のあったサービスは,通所介護,訪問\n介護,通所リハビリテーション,福祉用具,訪問看護,訪問リハビリテーションの順であった。\n効果のあるサービスの組み合わせには,「訪問介護と福祉用具」,「通所介護と福祉用具」であ\nった。サービス導入のタイミングは「入院や施設の退院,退所前に導入した」,「本人の意欲が\n出る前に導入した」が多かった。しかし,麻痺や循環器疾患をもつ利用者には退院・退所後本\n人が落ち着いてから導入することが自立につながることが明らかになった。以上より,今後,\nケアマネジャーは利用者のアセスメントを踏まえてサービスの早期導入や他職種との連携を深\nめていく必要がある。
続きを見る
|
|||
| 23.
論文 |
上山, 真美 ; 内田, 陽子 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,自宅で生活をしている認知症高齢者の排泄行動と家族の排泄介護に影\n響する要因を明らかにすることである。対象は,A町お
…
よびB町で開催された認知症の講習会\nに参加し,調査に同意を得た48人とした。方法は,自記式質問紙法とした。結果,自宅で生活\nをする認知症高齢者は,尿とりパッドを使用しながらトイレで排泄している者が多く,家族の\n介護では,時間を見はからい声をかけている者が多かった。認知症高齢者の排泄行動や家族の\n排泄介護に影響する要因としては,以下の2点が明らかとなった。①自力での排泄行動に影響\nする認知症高齢者自身の要因は,「年齢が高い」,「認知症のレベルが重い」,「手足の不自由さ\nがある」であった。②家族の排泄介護に影響する要因は,「認知症高齢者自身に手足の不自由\nさがある」,「介護する家族の年齢が高い」であった。
続きを見る
|
|||
| 24.
論文 |
内田, 陽子 ; 上山, 真美 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【目的】本研究の目的は, 看護学生の実習前後における認知症高齢者のアウトカム判定とケア実施率の関\n係を明らかにすることとした. 【対象と方法】対象は, A
…
大学3年生で調査協力の得られた38人の看護学\n生とその受け持ちの認知症高齢者38人である. 方法は, 学生に実習前後での受け持ち認知症高齢者の状況に\nついて「認知症ケアのアウトカム評価票」に記入してもらった. 【結果】アウトカム評価26項目の信頼性\n係数クロンバックα係数は, 1回目は0.85で2回目は0.83であった. アウトカム変化率で最高値維持が高\nかったアウトカム項目は, 「周辺症状(行動障害)」で, 改善は「コミュニケーション」, 「過去の趣味・生きが\nいの現実」, 維持は「着替え」, 悪化は「なじみの暮らし継続」, 最低値維持は「役割と発揮の有無」であった. \nケア実施率では,『目をみて話す』が高かった. 【結語】実習においては認知症高齢者の「コミュニケー\nション」等の改善が期待でき, 環境整備のケアは症状の改善をもたらす.
続きを見る
|
|||
| 25.
論文 |
内田, 陽子
概要:
application/pdf<br />Journal Article
|
|||
| 26.
論文 |
奥村, 朱美 ; 内田, 陽子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />本研究の目的は,介護老人保健施設入所中の認知症高齢者のニーズを明らかにし,ケアに必要なことを検討することである.対象は,A介護老人保健施設入所中の認知症をも
…
つ高齢者で,言語的コミュニケーションが可能なもの11名とした.方法は1対1の半構成的面接で情報を収集し,ニーズを現している言動を複数の研究者でカテゴリー化した.結果,ニーズとして,《人とつながっていたい》,《自分の生活の仕方・ペースを保ちたい》,《自分で何かやりたい》,《健康を保ちたい》,《周囲の人にはこのように自分と接して欲しい》,の5大カテゴリーが明らかになった.各ニーズの背景には介護老人保健施設入所中の認知症者の特徴がみられ,各ニーズの背景を考慮した工夫をケアに取り入れることが必要である.
続きを見る
|
|||
| 27.
論文 |
内田, 陽子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />本研究の目的は, 認知症ケアのアウトカム評価票原案の使用可能性を検討し, 案の改良を行うこととした.\n対象は看護学生及び看護師であり, 認知症ケアを実施し
…
た者で調査に協力を得られた67人とした. 方法は過\n去に受け持ったことのある認知症者の状況を振り返り, 認知症ケアのアウトカム票原案に沿って該当する番\n号を記入してもらった. 結果, 原案27項目の信頼性係数クロンバックα係数は0.889 であった. また, 1回目\nと2回目のアウトカム数値調査で項目得点間の相関係数は0.662~0.969 であった. 対象者からは原案につい\nて使用できるという高い回答を得た. また, アウトカム変化率を算出した結果, 最高値持続が高かったアウト\nカム項目は「挨拶」であり, 改善は「楽しいことに対する表現・笑顔」, 「外見の保持」であり, 維持は「入浴」, \n悪化は「なじみの暮らしの継続」, 最低値持続は「役割の有無と発揮」, 「金銭管理」が高い変化率であった. 無\n回答が多かった項目は, 「サービスへの満足度」, 「介護継続の意思」であり改良を行った.
続きを見る
|
|||
| 28.
論文 |
上山, 真美 ; 内田, 陽子 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,①看護学生が老年看護学実習において認知症高齢者にケアを実践した\nことによるアウトカムの変化とケア実施率,②改善がみ
…
られたアウトカム項目に対する学生の\nケア実施率を明らかにすることである。対象は,A大学4年生26名の看護学生とその受け持ち\nの認知症高齢者26名である。方法は,学生に高齢者の状態やケア内容をチェックする「認知症\nケアアウトカム評価票」の記入を,実習前後に求めた。結果,実習後のアウトカムが改善され\nた項目で多かったものは,「楽しい事に対する表現・笑顔」,「外見」,「過去の趣味・生きがいの\n実現」,「コミュニケーション」であった。この項目に対するケア実施率で高かったのは,『本\n人の好きな活動や会話を取り入れる』,『本人の過去・生い立ちの理解』,『整容を行う』,『訴え\nを聴く』などであった。反面,全体のアウトカム項目に対する『原因・背景の追究』などにつ\nいては,実施率が低かった。以上,教員は学生が高齢者のアウトカムを高められるようなケア\n実践ができるように支援していく必要がある。
続きを見る
|
|||
| 29.
論文 |
内田, 陽子 ; 斎田, 綾子 ; 河端, 裕美 ; 高橋, 陽子 ; 加藤, 綾子 ; 斉藤, 喜恵子 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,老人看護専門看護師コースにおける老年看護学実習のスタッフにもた\nらす効果を明らかにすることである。方法は調査に協力
…
を得た実習場のスタッフ29人を対象に\n質問紙調査による評価を行った。その結果,全体的にスタッフによる実習生のアセスメントや\n技術,アドバイス等の評価はよい傾向にあった。また,「看護・介護のアセスメント能力が向\n上した」,「自分達の看護・介護の問題点がわかった」,「よい看護・介護の方法がみつかった」\nというスタッフ自身へのよい変化がみられた。今後,一層,実習が高齢者やスタッフによい影\n響をもたらすよう実習方法を検討する必要がある。
続きを見る
|
|||
| 30.
論文 |
内田, 陽子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【目的】認知症ケアのアウトカム項目を明らかにし, アウトカム評価票原案を開発することを目的とした.\n【方法】文献検討, 質問紙調査, 専門家による検討によ
…
り進められた. 【結果】既存の文献では認知症症\n状, 生活行動, 幸福感, QOL, 介護負担の領域にアウトカムがまとめられた. 認知症ケア経験者対象239 人から\nは, 精神的安定, 生活行動, 認知症症状, 在宅療養継続などのアウトカムが明確になった. また, 在宅で認知症\nケア経験者25人からは「笑顔, 不安なく安心して暮らせる, 楽しく喜ぶ」に重要度が高かった. 【結語】専\n門家の検討により, 最終的に以下の特徴をもった認知症ケアのアウトカム評価票を作成できた. ①アウトカ\nムの主項目は「認知症症状・精神的安定」, 「生活・セルフケア行動」, 「その人らしい生活」, 「介護者の負担」\nで構成された. ② 2時点の状態をアセスメントし, 該当する番号を書き, 両者を比較して最高値持続, 改善, 維\n持, 悪化, 最低値持続と判定する. ③アウトカムを高めるためのケア項目を設定した.
続きを見る
|
|||
| 31.
論文 |
内田, 陽子 ; 小泉, 美佐子 ; 新井, 明子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,老年看護学教育においておむつ体験を導入し,この体験における学生\nの不快感の特徴と排泄ケアの学びについて明らかにする
…
ことである。対象は,群馬大学2年生\n164人の看護学生であり,排尿日誌の記載とおむつ装着して後始末までの不快感を調査票に記\n入させた。おむつ体験は2回実施し,1回目は紙おむつと尿とりパッド,2回目は紙おむつの\nみの体験をしてもらった。結果,不快感が100%と高い事項は,排尿直後及び60分後のパッド\nを交換したい気持ちであった。2回目に有意に不快感が低下していたのは,スムーズな装着,\n装着したときの違和感,尿意から排尿までの時間間隔等であった。学生の学びでは,排尿状況\nの理解が深まった,おむつ装着者の身体的ケア,尊厳の保護,おむつのすばやい交換,排泄の\n自立等がみられた。
続きを見る
|
|||
| 32.
論文 |
内田, 陽子 ; 上山, 真美 ; 富沢, 順 ; 石川, 徹
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />背景・目的】 現在, 寝たきり患者などの移動の際にバスタオルを使用している所が多い. 本研究の目的は, バスタオルにかわる患者仰向け体位からの移動兼療養用ウ
…
ールボアマットを開発し, その評価を行うこととした. 【対象と方法】 10人の健康学生を対象にバスタオルとウールボアマットの強度・耐性と体圧, 主観的評価を行った. 【結 果】 ウールボアのほうがバスタオルよりも長さ・幅方向で高い強度を示し, 伸び率も高かった. また, 何も敷かない場合とウールボアマットを敷いた場合では, 右踵部と左肘関節部において後者の方が体圧は低かった (p<0.05~0.01). また, バスタオルとウールボアマットの比較でも後者のほうが左肘関節で低い値が得られた (p<0.05). 被験者はウールボアのほうが肌さわり, 寝心地, 暖かさの面でよいと評価し, 首の安定感, 身体の痛み等もよいという者が多かった. また, 看護者側も持ちやすいという評価をしていた. 反面, ウールボアのほうが滑りやすいという意見もあった. 【結 語】 移動用兼療養においてはバスタオルよりウールボアマットのほうが適している.
続きを見る
|
|||
| 33.
論文 |
町田, 久美子 ; 内田, 陽子 ; 小谷, 弥生
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【目 的】 本研究の目的は, 認知症高齢者の買い物・金銭管理におけるできる・できない行動特性を明らかにすることである. 【対象と方法】 対象はBグループホー
…
ム入所者及びC認知症専用デイサービス利用者22人である. 方法は野菜や果物等の実物, 魚や肉などのフードモデルを使用して模擬店を開催し, 2000円以内で今晩のおかずの買い物をしてもらった. 評価は一連の買い物・金銭管理行動の構成要素を手順化し, チェックリストを作成して観察記録した. チェックリストの項目は『準備』『選択・判断』『支払い』の大項目と, 大項目の行動を分類した合計30個の小項目から構成されている. 【結 果】 できた行動は, 30項目中9項目で『選択・判断』が最も多かった. できなかった行動は, 30項目中1項目のみで「かごを持ち歩きながら買い物をする」ことであった. 【結 語】 認知症高齢者ができる買い物・金銭管理行動特性を活かして, 日常生活で実際に繰り返し実践することが重要である.
続きを見る
|
|||
| 34.
論文 |
内田, 陽子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【背景・目的】 本研究の目的は, ケアマネジャーからみた自立支援, 介護予防の条件を明らかにすることである. 【対象と方法】 対象は群馬県主催のリーダー研修
…
に参加したケアマネジャー 67人に対して, 自立支援, 介護予防ができたと判断された事例の調査表の記入を依頼した. 分析対象はそのなかで同意を得られた35事例とした. 方法は利用者背景条件, アウトカム, 利用サービス, ケアプランの内容から構成する調査表をもとにケアマネジャーに条件分析のグループワークを行った. 【結 果】 自立支援・介護予防できたとケアマネジャーが判断した事例は, 寝たきりになる前の認知症が軽度の者が多かった. また, 主疾患は筋骨格疾患が多く, 主介護者の健康状態や本人との人間関係も良好なものが多かった. サービスは全員福祉用具を利用し, アウトカムの内容には本人の介護度, 歩行, 閉じこもり, 入浴, 意欲, 在宅生活の継続, 排泄, 転倒の改善が記述されていた. その条件の占める割合で高かったものは(1)ケア提供者, (2)本人・家族, (3)ケアマネジャーの条件の順であった. ケア提供者の条件ではサービスの工夫, 状態に合わせた福祉用具の活用, スタッフの声かけ, 訪問介護やリハビリが適切であった. 本人・家族の条件には家族の協力, 本人の意欲があった. ケアマネジャーの条件には, 本人・家族及び事業所との連絡, 効果的なサービスの組み合わせ, 量の調整をした等が明らかになった. 【結論】 今後, これらの条件を考慮したケアマネジメント, サービス提供を行う必要がある.
続きを見る
|
|||
| 35.
論文 |
内田, 陽子 ; 磯田, 哲夫
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【背景・目的】 本研究の目的は, 優光商会が開発した自分流枕の癒しと睡眠の主観的評価, 及び看護へ応用するための改良点を明らかにすることである. 【対象と方
…
法】 方法は健康人31人を対象にし, 自分流枕と普段枕を使用して, 7日間連続して調査票への記入を依頼した. 調査票は睡眠に影響を与える背景条件, 枕を使っての寝つきや熟睡感, 枕の高さや肌さわり, 癒された感じなどの主観的評価項目から構成されている. 【結 果】 熟睡感, 枕の高さ, 肌さわり, 居心地, 癒された感じについては自分流枕のほうがよい評価が得られた. 特に肌さわり, 居心地, 癒された感じについては初日から普段の枕に比べて有意な差がみられた. 逆に取り扱いの面倒さは, 自分流枕のほうが面倒であると感じる者が多かった. 【結 論】 自分流枕の主観的評価は高かった. この枕を改良して, 術後患者の安楽枕等への活用の可能性が考えられた. また, 高さ調整の際に小さなパイマーがこぼれ, 乳児や高齢者が謝って口にする可能性があり改良が必要である.
続きを見る
|
|||
| 36.
論文 |
内田, 陽子
概要:
application/pdf<br />Journal Article
|
|||
| 37.
論文 |
内田, 陽子 ; 新井, 明子 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,老年実習における学生のヒアリハットの場面と内容を明らかにし,教育方法を検討することである。対象は協力の得られた本学6
…
期生75人であり,実習中にヒアリハット体験を調査票に記載してもらった。結果,以下のことが明らかになった。1.関連するリスクは転倒・転落が一番多く,ついで誤嚥,外傷,利用者取り違え等であった。2.ヒアリハット体験場面は,入浴,食事,排准などの日常生活援助場面が多く占めた。3.ヒアリハットの件数に比べ教員や職員に対する報告件数は少なかった。対策として学生の確認や技術練習を重ねるとともに,事前に予測されるリスク表を手渡し,実習中に確認させる。実習中にいつでも教員や職員に相談,確認できる体制を整えることが必要と考えた。
続きを見る
|
|||
| 38.
論文 |
内田, 陽子 ; 新井, 明子 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は群馬大学医学部保健学科での老年看護学実習の評価を行い,学生の高齢者に対する看護実践のやる気を高める条件を明らかにするこ
…
とである。対象は2004年5月から7月にかけてS介護老人保健施設で実習をした39人の本大学の学生である。調査は学生の実習終了最終日に学生に質問紙を配布し,各自記入をしてもらった。質問紙の主な調査項目は,(1)学生の高齢者看護実践のやる気の程度と,それに影響する条件として(2)学生の背景条件,(3)受け持ち高齢者の背景条件,(4)実習における学習の程度に関する項目を設定した。結果,1,学生にとって受け持ち高齢者へのアセスメントや看護実践に対しては教員が,他の高齢者に対する看護実践では看護師が有効であると認識していた。 2,学生の看護過程や技術に対しての自己評価は高かった。3,痴呆棟に実習に行った学生のほうが,高齢者から拒否された経験が生かされ関わる自信がついていた。4,学生の今後の高齢者に対する看護実践のやる気と有意な正の相関がみられた項目は,「アセスメントができた」,「実習が楽しかった」,「介護老人保健施設に就職したい」,「元来実習が好きである」,「受け持ち高齢者に拒否された経験があった」,「受け持ち高齢者に対する看護技術の実践」であった。「受け持ち高齢者の排泄が自立している」については負の相関がみられた。5,学生のやる気はグループ毎に相違があり,最も有効なやる気を高める条件は「実習が楽しかった」であった。痴呆高齢者に拒否されても,日々のケアのなかで患者と分かり合えることを促す指導を実践していくことが求められる。教員は授業としての実習を展開するなかで,学生の気持ちや表情を観察し,学生が問題解決のどの過程にあるか,満足いく実習ができているか常に確認していく必要がある。
続きを見る
|