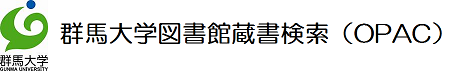※一部利用できない機能があります
| 1.
論文 |
二渡, 玉江 ; 砂賀, 道子 ; 堀越, 政孝 ; 武居, 明美 ; 高橋, 陽子 ; 廣瀬, 規代美 ; 中西, 陽子 ; 神田, 清子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【目的】1999年から2008年までに日本国内で掲載された乳房温存術を受けた乳がん患者の看護に関する論文から, 研究の動向と課題を明らかにする. 【方法】「
…
医学中央雑誌」を使用し,「乳がん」「看護」「乳房温存術」「乳房温存療法」をキーワードに検索を行い, 研究デザイン, 方法, 内容の分析を行った. 【結果】対象文献は49論文であり, 量的研究が53.1%と半数以上を占め, 研究デザインは, 因子探索的研究が最も多く57.1%であった. 研究内容は「心理的変化とストレスコーピング」(18コード : 36.7%),「治療に伴う機能障害の予防と生活への影響」(7コード : 14.3%),「治療選択やQOLに影響する要因」(8コード : 16.3%),「治療に関連した情報提供と支援ニーズ」(5コード : 10.2%),「看護介入プログラムの開発とケア実践の評価」(11コード : 22.4%) の5つのカテゴリに集約された. 【考察】以上の結果は, 乳房温存術や継続治療がもたらす心身両面への影響をQOLの視点から捉え, 心理的な看護介入プログラムによる介入研究がなされるようになってきていることを示している. 今後は介入研究を積み重ね, それらの評価に基づく効果的な介入プログラムの開発が望まれる.
続きを見る
|
|||
| 2.
論文 |
恩幣, 宏美 ; 武居, 明美 ; 堀越, 政孝 ; 辻村, 弘美 ; 神田, 清子 ; 二渡, 玉江 ; 森, 淑江 ; 岡, 美智代
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />【目的】本研究は,成人看護学実習を履修した看護学生における,ヒヤリハットに対す\nる知識と認識を明らかにし,今後の成人看護学領域にお
…
ける医療事故に対する教授方法の検討\nに活かすことである。【方法】2008年にA大学医学部保健学科の成人看護学実習を履修した学\n生に,医療事故の事例を読んでもらい,フォーカスグループインタビューの実施またはレポー\nトを提出してもらった。それらの内容から認識と知識を抽出し,KJ法で分析を行った。【結果】\n知識は2カテゴリーに分類され,認識は8カテゴリーと26サブカテゴリーに分類された。【結\n論】学生は実習前に学習した知識を有しながらも,その知識を有効に活用することができない\n認識の中で実習を開始し,患者・家族や看護師,教員との相互関係の中でヒヤリハットに対す\nる様々な認識を持っていることが明らかとなった。教員は学生がこれらのヒヤリハットに対す\nる知識と認識をもっていることを理解しながらも,まずはヒヤリハットや医療事故を防ぐ具体\n的な取り組みを講じていくことが重要である。
続きを見る
|
|||
| 3.
論文 |
堀越, 政孝 ; 辻村, 弘美 ; 恩幣, 宏美 ; 武居, 明美 ; 斉藤, 洋子 ; 岡, 美智代 ; 神田, 清子 ; 森, 淑江 ; 二渡, 玉江
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />〔目的〕成人看護学実習Ⅱに組み込まれている手術室見学実習において,学生が手術室\n看護師の役割や手術侵襲・合併症について,どのような
…
学びを得ているかを明らかにすること\nである。〔方法〕手術室見学実習を行った学生のレポートを分析対象とし,学びに関する文章\nを抽出した。抽出した文章を1文脈単位に分けて記録単位とし,Berelson,B.の内容分析を\n参考に意味内容の類似性に従い抽象化し,カテゴリを導き出した。〔結果〕手術室見学実習に\nおける学生の学びは,【術前における外回り看護師の業務】【手術により起こりうる合併症】\n【手洗い看護師の業務】【手術室におけるチームワーク】【術中・術直後における外回り看護師\nの業務】【手術に伴う患者の身体的・精神的苦痛】【学生が実感した手術室見学実習の効果】\n【手術室環境に関する情報】【回復室看護師の業務】【手術室看護師に求められる能力】の10カ\nテゴリに分類され,37サブカテゴリが含まれた。〔結語〕手術室見学実習における学生の学び\nを分析した結果,多くの学生が掲げた行動目標を全て達成できていた。また,より実践的な学\nびを提供するためには,実習体制の整備が必要と考えられた。
続きを見る
|
|||
| 4.
論文 |
神田, 清子 ; 二渡, 玉江 ; 武居, 明美 ; 堀越, 政孝 ; 瀬山, 留加
概要:
application/pdf<br />Journal Article
|
|||
| 5.
論文 |
辻村, 弘美 ; 堀越, 政孝 ; 武居, 明美 ; 恩幣, 宏美 ; 神田, 清子 ; 岡, 美智代 ; 二渡, 玉江 ; 森, 淑江
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,2005年入学の新カリキュラム導入後の学生(以下新カリ群)の成人看\n護学急性期実習と慢性期実習における看護基本技術
…
の経験度を明らかにし,成人看護学実習に\nおける看護実践能力育成についての今後の課題を検討することである。2005年入学の看護学専\n攻の学生を対象に,80項目の看護基本技術についてその経験度を学生本人が実習終了後に評価\nし,新カリキュラム導入前の2004年入学の学生(以下旧カリ群)との比較を行った。旧カリ群\nとの比較では,急性期実習では,80項目中13項目に経験度に有意差があり,そのうち新カリ群\nの方が有意に高かった項目は〈検体の採取と扱い方(採血・血糖検査)〉,〈経皮的非侵襲的検\n査時の援助(心電図モニターなど)〉,〈医療廃棄物管理〉の3項目,また慢性期実習では,80\n項目中8項目に有意差があり,そのうち新カリ群の方が有意に高かった項目は〈包帯法〉,〈検\n体の採取と扱い方(採血・血糖検査)〉の2項目のみで,新カリ群の経験度が旧カリ群よりも\n有意に低かった。以上より,旧カリ群のほうが成人看護学実習において多くの経験をしている\nことが明らかになった。この背景には新カリキュラムによる実習期間の変更が影響したことも\n考えられ,成人看護学実習における看護技術習得分野の見直しの検討や実習指導体制の強化な\nどが指摘された。
続きを見る
|
|||
| 6.
論文 |
二渡, 玉江 ; 堀越, 政孝 ; 武居, 明美 ; 神田, 清子
概要:
application/pdf<br />Journal Article
|
|||
| 7.
論文 |
神田, 清子 ; 武居, 明美 ; 狩野, 太郎 ; 石田, 和子 ; 平井, 和恵 ; 二渡, 玉江
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【目的】外来で化学療法を受ける療養者が急増し, 症状マネジメントが療養の場である在宅に移行してい\nる. 看護者には対象者の能力を引き出し, 症状マネジメン
…
ト力を高める支援が求められている. 本研究の目的\nは, がん化学療法を受けている療養者のセルフマネジメントに関連する2002年から2006年までの原著論文\nを分析し, 研究課題を明確にすることである. 【方法】「医学中央雑誌」を使用し,“化学療法”“通院治療”\n“セルフマネジメント”をキーワードに検索を行い, 研究デザイン, 方法, 内容の分析を行った. 【結果】\n該当文献は35論文であり, 研究デザインは因子探索研究, 種類は質的研究が約60%を占めていた. 研究内容\nは, 化学療法の副作用が療養者の身体, 心理・精神, 社会に与える影響とその対処の現象を明らかにした研究\nが45.7%であり, 次いで, セルフマネジメントを促進する介入効果の研究25.7%であった. 家族を対象とした\n研究やエビデンスレベルの高い研究は少ない状況であった. 【結語】心理・教育的介入, 家族およびソー\nシャルサポートを焦点としたエビデンスレベルの高い研究が必要であることが示唆された.
続きを見る
|
|||
| 8.
論文 |
武居, 明美 ; 佐名木, 宏美 ; 辻村, 弘美 ; 堀越, 政孝 ; 反町, 真由 ; 岡, 美智代 ; 森, 淑江 ; 二渡, 玉江 ; 神田, 清子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />[目的]外来化学療法センター実習の記録から,がん化学療法が患者に及ぼす影響に関\nする学生の学びを明らかにする[方法]看護学生60名
…
が記録した外来化学療法センター実習の\n記録から明らかになった240の学びについて内容分析を行った。[結果]化学療法が患者の生活\nに及ぼす影響の学びは6つのサブカテゴリーに分類され,【化学療法が心理・精神,生理,社\n会生活に負の影響を与えていることの理解】【生活を再調整する必要性の理解】【治療や疾患に\n対して不安を抱くことの理解】の3カテゴリーが形成された。患者が自ら行っている対応方法\nの学びは9サブカテゴリーに分類され,【副作用や治療で生じた負の影響に対する対応の理解】\n【ストレスマネジメントや生活リズムの獲得と適応の理解】【治療生活と自己コントロール感の\n獲得の理解】の3カテゴリーが形成された。[結語]成人看護学実習Ⅰの行動目標と比較した\nところ,目標に沿った学びが得られていた。【生活を再調整する必要性の理解】についての記\n録単位数が少なく,今後は事前学習で学生の生活の再調整への意識を高め,より有意義な実習\nとしていく必要性が示唆された。
続きを見る
|
|||
| 9.
論文 |
佐名木, 宏美 ; 武居, 明美 ; 堀越, 政孝 ; 辻村, 弘美 ; 田村, 良子 ; 塚越, 聖子 ; 神田, 清子 ; 二渡, 玉江 ; 森, 淑江 ; 岡, 美智代
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />【目的】本研究は,成人看護学実習Ⅰの中で取り組んだ外来継続看護実習,特に人工腎\n臓センターにおける透析看護や透析患者の生活に対する
…
学生の学びや気づきを明らかにするこ\nとである。【方法】看護系大学3~4年次に在学する学生の人工腎臓センターにおける実習記\n録の中から,気づきと学びを抽出し内容分析を行った。【結果】学生の学びや気づきは17サブ\nカテゴリに分類され,意味内容の類似性により,「その人らしい生活や人生を送ることの重要\n性に対する学び」「食事・水分などの自己管理に対する学び」「患者を支える社会システムや家\n族の重要性に対する学び」「透析治療に伴う苦痛に関する学び」「患者の生活に合わせたセルフ\nケア能力向上への援助に対する学び」「家族看護の重要性に対する学び」「苦痛や不安を抱えた\n患者が前向きに生活するための精神的サポートに対する学び」の,7つのカテゴリに統合され\nた。その中でも,「食事・水分などの自己管理に対する学び」のカテゴリは,全記録単位数の\n28.9%であり,全てのカテゴリの中で最も多かった。【結語】人工腎臓センターにおける学生\nの学びと気づきから明らかとなったことは,学生は厳しい制限の中でも,自分らしく生活する\nことの素晴らしさと困難さについて理解していた。
続きを見る
|
|||
| 10.
論文 |
堀越, 政孝 ; 辻村, 弘美 ; 武居, 明美 ; 佐名木, 宏美 ; 松井, 佐知子 ; 鈴木, 伸代 ; 岡, 美智代 ; 神田, 清子 ; 森, 淑江 ; 二渡, 玉江
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,ストーマケア外来実習記録に記載されている学生の学びに関する文章\nを抽出し,その学びの内容を明らかにすることである。
…
看護学専攻の大学生59名を対象とし,\n内容分析の手法を用い,実習後記録の「実習を通して学んだ点」の項目に書かれてある内容を\n中心に学生の学びを抽出,分析した。その結果,総数561記録単位,27サブカテゴリが得られ\nた。これらは【ストーマケア外来の役割と提供されるケア】【ストーマケアを行う看護師に求\nめられる能力】【継続看護の重要性】【患者のストーマに対する思いや対応】【ストーマの状態\nや問題】【ソーシャルサポートの必要性】の6カテゴリに分類された。学生は,対象者である\n患者のストーマを観察することでその状態や問題点を把握し,さらに患者の抱える不安,戸惑\nいなどの思いやストーマに対する患者なりの工夫などを学んでいた。また,実習指導を担当し\nている皮膚・排泄ケア認定看護師の患者との関わりの場面から,高度な専門性を備えた看護師\nの役割やケア,継続看護の意義やその必要性,さらには患者を取り巻く家族などの協力が必要\nなことを学んでいた。
続きを見る
|