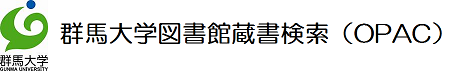※一部利用できない機能があります
| 1.
論文 |
TAKAHASHI, Tamami ; ARAI, Yoshihiro ; 高橋, 珠実 ; 新井, 淑弘
概要:
Departmental Bulletin Paper<br />本研究は、さまざまな分野で注目されるマインドフルネスを用いたメンタルトレーニングの効果を検討することを目的とし、マインドフルネスを用いたメンタルトレーニングが女子大学生アスリ
…
ートの身体組成、心理面、および生活習慣面にどのような影響を与えるのか検討を行った。\n T大学の女子大学生アスリートを対象にメンタルトレーニング群は5週間のメンタルトレーニング(約20分)を行い、メンタルトレーニングを行わないコントロール群との比較を行った。両群ともに実験期間前後に身体組成測定、心理調査(POMS2)を行い、実験期間後に約5週間の体調面、心理面、生活習慣等の変\n化に関するアンケートを行った。\n マインドフルネスを用いたメンタルトレーニングが女子大学生アスリートの身体組成、および心理面、生活習慣面にポジティブな変化をもたらしたことから、競技パフォーマンスに好影響を与える可能性が明らかになった。
続きを見る
|
|||
| 2.
論文 |
Noda, Tomoko ; Kamata, Hisako ; 野田, 智子 ; 鎌田, 尚子
概要:
Journal Article<br />【目的】特別支援学校肢体不自由部門に通学する中高等部生(12~17歳) の障害と生活習慣の実態を明ら\nかにし, その問題点について検討する. 【対象と方法】A 県特別支援学校肢体不自由部門4校に通
…
学する中\n高等部生徒の保護者と担任・養護教諭を対象に質問紙調査を行い, 単純集計により分析を行った. 【結果】\n回答者数は104名であった. 起因疾患は脳神経疾患が76.9%と多く, 移動機能は寝たきりの者が49.0%, 教科\n以外の教育課程の者は85.6%であった. また, 筋緊張の異常を有する者が76.9%, 脊柱側弯を有する者が73.\n1%, BMI パーセンタイルが5パーセンタイル未満の者は62.5%で, 対象児の思春期以降のQOL の向上には,\n筋緊張の亢進を緩和して脊柱側弯の進行を防止することと, 栄養管理の重要性が示唆された. 生活習慣に関\nする調査からは, 生活習慣上の問題点が3つ抽出された. 第1は「登校時間が長く, 同一姿勢で過ごすことが\n多い」で,筋緊張の亢進と脊柱側弯の進行への影響が懸念された.第2は「間食内容の不十分さ」,第3は「社\n会サービス利用の少なさ」であった. 【結語】以上から,通学用バスの収容人数を少なくし,通学時間を短\n縮するなどの対応が必要と考えられた. また, 朝昼夕の3食に間食を加えて計画的に栄養管理していくこと\nの必要性が示唆された. さらに, 卒業後の対象児と家族の生活を見通し, 学齢期から社会サービスの利用に慣\nれておくことが必要と考えられた.
続きを見る
|
|||
| 3.
論文 |
Murayama, Yuri ; Yamamoto, Rinko ; Yamaguchi, Miho ; Yamazaki, Chiho ; Nakazato, Minato ; Koyama, Hiroshi ; 村山, 侑里 ; 山本, 林子 ; 山口, 美穂 ; 山崎, 千穂 ; 中澤, 港 ; 小山, 洋
概要:
Journal Article<br />[背景・目的]日本の農村部においては白殺が大きな社会問題となっており,それに関連する抑うっ状態へ\nの対応やうつ予防が重要な健康問題となっている.原因となるライフスタイル要因は性別や年齢層によって\
…
n大きく異なるものと考えられ,本研究では,性・年齢別に抑うつ状態とライフスタイル要因との関連について\n解析を行い,性・年齢別の関連構造の特異性および共通性を明らかにすることを目的とした.[対象と方法]\n群馬県K村の住民健康診断受診者(男性144名,女性217名,平均年齢58.5歳)を対象に質問紙による調査を\nおこなった.質問紙は健康チェック票THIからの抑うつ尺度10項目(THI-D)を含む自記式質問票「こころ\nのチェックシート」を用いた.男女それぞれを60歳未満・60歳以上に層化し,層ごとにライフスタイル要因\nの変数と抑うつ尺度の関連性を順位相関係数によって検討した後,Rの拡張パッケージsemを用いて共分散\n構造分析を行った.[結 果]抑うつ尺度と関連性が認められたライフスタイル要因は,仕事上の心配,対\n人関係の悩み,幸福感,同居人数,通院,疾病苦,親戚友人数,睡眠,飲酒,運動であった.性・年齢層ごとの4群\n別々に共分散構造分析を行い,各群とも十分な説明力をもっモデルが得られた.全ての群で共通して抑うつ\n状態と関連が認められた因子は「対人関係の悩み」と「仕事上の心配」であった.これらの要因は潜在因子「社\n会的機能不全」を介して抑うつ尺度の高さに影響を与えていた.「社会的機能不全」と抑うつ尺度の高さは正\nの相関関係にあることが示された.各群の特徴的な潜在因子および関連構造としては,1)60歳未満の男性に\nついてのモデルでは飲酒頻度や適切な睡眠時間が潜在因子「生活上のゆとり」を介して抑うつ尺度の低さと\n関連,2)60歳以上の男性では非独居であることと親戚友人数の多さが潜在因子「対人艮好性」を介して抑う\nつ尺度の低さに関連,3)60歳未満の女性では「通院」していることと「疾病苦」を有することが潜在因子「有\n病状態」を介して抑うつ尺度と関連,4)60歳以上の女性では「親戚友人数」の少なさと「疾病苦」の高さが\n潜在因子「内向性」を介して抑うつ尺度と正の関連を有することが示された.[結 語]抑うつ状態に共通\nして関連するのは対人関係の悩み・仕事上の心配であるが,関連するライフスタイル要因の構造は性・年齢群\nによって異なることが示された.抑うつ状態に対する支援やうつ病予防対策は性・年齢ごとに適した対応が\n求められると考えられた.
続きを見る
|