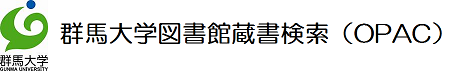※一部利用できない機能があります
| 1.
論文 |
Kondo, Horoko ; Tsujimura, Hiromi ; Ushikubo, Mitsuko ; Yoshida, Tohru ; Sakou, Keiko ; Tokiwa, Yoko ; Kanda, Kiyoko ; 近藤, 浩子 ; 辻村, 弘美 ; 牛久保, 美津子 ; 吉田, 亨 ; 佐光, 恵子 ; 常盤, 洋子 ; 神田, 清子
概要:
Journal Article
|
|||
| 2.
論文 |
Kondo, Hiroko ; Yoshida, Toru ; Tsujimura, Hiromi ; Sakou, Keiko ; Tokiwa, Yoko ; Hakozaki, Yumi ; Kubo, Hitomi ; Kanda, Kiyoko ; 近藤, 浩子 ; 吉田, 亨 ; 辻村, 弘美 ; 佐光, 恵子 ; 常盤, 洋子 ; 箱崎, 友美 ; 久保, 仁美 ; 神田, 清子
概要:
Journal Article<br />目 的:本研究の目的は,群馬県内病院看護職の在宅を見据えた看護活動の実態および 4 年間の縦断的変化を明らかにすることであった.方 法:県内 11 病院の看護職を対象に質問票調査を 2 回実施した.
…
結 果:回答は,2014 年が 2,136件(回収率 73.3%),2018 年が 2,399 件(回収率 77.8%)であった.在宅を見据えた看護活動のうち,『在宅生活の情報把握』と「患者への説明をサマリーに記載すること」は実践度が高く,一方,『社会資源の活用』と「住宅地域や自宅構造の把握」,および「継続できる薬剤使用の相談」は実践度が低かった.また看護活動実践度の高さは,年齢の高さ,経験年数の長さ,看護管理職の職位,在宅看護研修の受講と関連していた.結 論:2 回の調査間で看護活動実践度が有意に上昇したのは,スタッフの職位と 2014 年に実践度の低かった施設であった.今後は,経験や役割等に応じた看護活動実践度を示せるよう,さらに解析を進めたい.
続きを見る
|
|||
| 3.
論文 |
Horikoshi, Setsuko ; Tokiwa, Yoko ; 堀越, 摂子 ; 常盤, 洋子
概要:
Journal Article<br />目 的:本研究の目的は,乳幼児をもつ母親の育児に伴うストレスマネジメントの概念を明らかにすることである. 方 法:国内外の 34 文献を対象とし,Rodgers の概念分析の手法を用いて分析を行った
…
. 結 果:概念の属性は【育児に伴うストレス状況に応じた対処行動の工夫】であった.先行要件は【育児の中で感じるストレスの存在】【育児に伴うストレスの自覚】【育児に伴うストレスへの対処可能性の認識】であった.帰結として【育児に伴うストレスの軽減】【母親の心理的健康の維持・向上】【育児に関する自己効力感の向上】が導かれた. 結 語:本研究における概念分析の結果得られた育児に伴うストレスマネジメントの概念は,乳幼児をもつ母親が育児に伴うストレスを自覚し,ストレスへの対処が可能であるという認識を抱くことで,様々な対処行動の中から自身に適した方法を選択・実行し,実行した対処行動を振り返り修正しながら育児に伴うストレス状況に応じて対処行動を使い分け,対処行動を工夫することである.本概念を基に,育児に伴うストレスマネジメントを「育児に伴うストレスを自覚し,ストレスへの対処可能性を認識し,育児に伴うストレス状況に応じて対処行動を工夫すること」と定義した.社会環境の変化により母親の育児の負担感が増し,母親が育児に伴うストレスをマネジメントできるように支援していくことは今後ますます重要となることが予測されるため,本概念は母親支援ならびに育児に伴うストレスマネジメントに関する研究への活用性が期待できる.
続きを見る
|
|||
| 4.
論文 |
高田, 幸子 ; 塚越, 聖子 ; 今井, 裕子 ; 常盤, 洋子 ; 中村, 美香 ; 金井, 好子 ; 大谷, 忠広 ; 冨田, 千恵子 ; 貞形, 衣恵 ; 瀬沼, 麻衣子 ; 坂口, 千恵美 ; 深澤, 友子 ; 塚越, 徳子 ; 箱崎, 友美 ; 冨丘, 洋子 ; 佐藤, 綾子 ; 神田, 清子
概要:
Journal Article
|
|||
| 5.
論文 |
深澤, 友子 ; 常盤, 洋子 ; 中村, 美香 ; 塚越, 聖子 ; 今井, 裕子 ; 金井, 好子 ; 大谷, 忠広 ; 冨田, 千恵子 ; 貞形, 衣恵 ; 瀬沼, 麻衣子 ; 坂口, 知恵美 ; 牛久保, 美津子
概要:
Journal Article<br />【目的】地域包括ケアシステムの構築が推進される中, 病院看護職は地域完結型の看護実践が求められる. 本研究では大学病院看護職員における地域完結型看護人材養成プログラム(履修証明プログラム, 大学院コ
…
ース) の周知状況の実態を明らかにする.【方法】A 大学附属病院看護職員751名に無記名自記式質問票調査を実施した.【結果】回収数は674部(回収率89.7%)で,667部を分析対象とした(有効回答率98.9%).履修証明は305名(45.7%),大学院は395名(59.2%)に周知され,受講希望・検討中は履修証明149 名(22.3%),大学院119 名(17.8%),受講を悩む理由は,仕事と学業両立への不安が最多だった. 在宅ケアマインドは231名(34.6%) に周知されていた.【結論】附属病院看護部と大学の地域完結型看護人材養成のための協働体制を活かした周知活動が現任教育の動機づけを高めることが示唆された.
続きを見る
|
|||
| 6.
論文 |
Ohtani, Tadahiro ; Ushikubo, Mistuko ; Horikoshi, Masataka ; Kanai, Yoshiko ; Tomita, Chieko ; Sugimoto, Atsuko ; Onoue, Etsuko ; Ogiwara, Kyouko ; Sakou, Keiko ; Kondo, Hiroko ; Tokiwa, Youko ; Kanda, Kiyoko ; 大谷, 忠広 ; 牛久保, 美津子 ; 堀越, 政孝 ; 金井, 好子 ; 冨田, 千恵子 ; 杉本, 厚子 ; 尾上, 悦子 ; 荻原, 京子 ; 佐光, 惠子 ; 近藤, 浩子 ; 常盤, 洋子 ; 神田, 清子
概要:
Journal Article
|
|||
| 7.
論文 |
堀越, 摂子 ; 常盤, 洋子 ; 國清, 恭子 ; 高津, 三枝子
概要:
Journal Article<br />目的:生後1か月の児を育てている母親の児の泣きに関する認識を明らかにすることである.研究方法:研究対象者は, 正期産にて出産し, 母児共に産後の経過が正常な母親10名である. 産後1か月健診時に,
…
研究対象者に半構成的面接調査を行い, ベレルソン(Berelson, B) の内容分析を用いて質的帰納的分析を行った.結果:生後1か月児の泣きに関する母親の認識の内容として,【泣くことは当たり前のことであるという考え】,【家族の手助けがあることからくる安心】,【児の泣きに母親が一人で対処することの困惑】,【自分自身で児の泣きに対処しようという考え】,【児が泣いていることに対する満足】,【思い通りに児の泣きに対処しなければいけないという考え】,【対処することで泣き止むことからくる安堵】,【泣き声で迷惑をかけないようにという周囲への気遣い】という8つのカテゴリが形成された.結語:生後1か月の児を育てている母親は, 家族から手助けを受けたり, 児の泣きに対処できている状況では児が泣いても安心であると認識していた.一方,児の泣きに対して思い通りに対処しなければいけないと認識していた.さらに,児の泣きに対処できない場合には困難な思いを抱いていた. 母親が抱く自分の思い通りに対処しなければいけないという認識や児の泣きに対処できないかもしれないという認識を変化させることで, 否定的な感情の改善を図ることができると考えられる.
続きを見る
|
|||
| 8.
論文 |
近藤, 浩子 ; 牛久保, 美津子 ; 吉田, 亨 ; 豊村, 暁 ; 佐光, 恵子 ; 神田, 清子 ; 常盤, 洋子 ; 堀越, 政孝 ; 松崎, 奈々子
概要:
Journal Article
|
|||
| 9.
論文 |
堀越, 政孝 ; 常盤, 洋子 ; 牛久保, 美津子 ; 近藤, 浩子 ; 松崎, 奈々子 ; 吉田, 亨 ; 豊村, 暁 ; 佐光, 恵子 ; 神田, 清子
概要:
Journal Article
|
|||
| 10.
論文 |
大谷, 忠広 ; 牛久保, 美津子 ; 金井, 好子 ; 冨田, 千恵子 ; 杉本, 厚子 ; 尾上, 悦子 ; 荻原, 京子 ; 佐光, 恵子 ; 近藤, 浩子 ; 常盤, 洋子 ; 神田, 清子
概要:
Journal Article
|
|||
| 11.
論文 |
Takatsu, Mieko ; Kunikiyo, Kyoko ; Hayashi, Kaori ; Tachiki, Kaori ; Fukasawa, Tomoko ; Tikiwa, Yoko ; 國清, 恭子 ; 林, かおり ; 立木, 香織 ; 深澤, 友子 ; 常盤, 洋子
概要:
Journal Article<br />【目的】初産婦が保健行動をとる際の動機,負担を明らかにし,妊婦の保健行動の実態に即した保健指導のあり方を検討する資料を得ることを目的とする.【方法】妊娠 30週~34週の妊婦 10名を対象に,初妊婦
…
が保健行動をとる際の動機と負担について,半構造化面接法によりデータを収集した.分析はベレルソンの内容分析を使用した.【結果】初産婦が保健行動をとる際の動機と負担について,①【妊娠中の身体と日常生活に関心をもって気を付けようとする動機】,②【医療従事者,夫や会社の人に指摘を受けたことに関連した動機】,③【出産・出産後に関連した自分の体と胎児の健康に関連した動機】,④【妊娠経過の変調の気づきに関連した動機】,⑤【出産体験のある実母や祖母など身近な人から妊娠中の体験を聞いたことに関連した動機】,⑥【仕事が負担になり妊娠期の保健行動がとれない負担】,⑦【食習慣や生活リズムの変更が自分でコントロールできない負担】という 7つのカテゴリーが得られた.【結語】初産婦が保健行動をとる際の動機と負担について得られた 7つのカテゴリーから,妊婦の保健行動は,食事,動静,生活リズムなど日常生活上の生理的欲求と関係する行動が多いことが明らかになった.初産婦への保健指導では,妊婦の日常生活と保健行動に関与する人間関係を考慮して,保健行動をとる際の動機になること,負担になることを把握し,妊婦自身が妊娠期の健康を意識できるような指導が必要であると考える.
続きを見る
|
|||
| 12.
論文 |
中島, 久美子 ; 澤野, 沙耶香 ; 國清, 恭子 ; 荒井, 洋子 ; 立木, 歌織 ; 深澤, 友子 ; 常盤, 洋子
概要:
Journal Article
|
|||
| 13.
論文 |
Suto, Kumi ; Hirakawa, Kimie ; Horigome, Kazuyo ; Kunikiyo, Kyoko ; Tokiwa, Yoko ; 須藤, 久実 ; 平川, 君江 ; 堀込, 和代 ; 國清, 恭子 ; 常盤, 洋子
概要:
Journal Article<br />【目的】出産体験の意味づけへの援助を検討するために, 出産体験の意味化の具体的内容を知る. 【方\n法】2005年8月~同年11月に, 早期産で低出生体重児を出産した母親を対象に半構成的面接により出
…
産体\n験を語ってもらい, Berelsonの内容分析を参考にしデータ化. 【結果】出産体験の意味化は〔早期産を意\n識したことに対する医療に頼った苦痛や安堵感〕〔早い週数での出産開始に対する専門家に頼った苦痛や安堵\n感〕〔ハイリスク状態の重症化に対する苦痛や保健行動〕〔早期産の子どもの発育の未熟さに対する苦痛や安\n堵感〕〔早い週数で緊急帝王切開で出産したことに対する子どもを出産した実感のなさ〕〔産後のマイナート\nラブルに対する苦痛や子どもへの接触時期の遅れ〕〔早期産を意識した夫の気持ちに対する負担感〕の7コア\nカテゴリーに分類された. 【結語】意味化の具体的内容は, 出産体験の意味づけへの援助を検討するアセ\nスメントの視点として活用できる.
続きを見る
|
|||
| 14.
論文 |
Nakajima, Kumiko ; Ito, Reiko ; Kunikiyo, Kyoko ; Arai, Hiroko ; Sakamoto, Shinobu ; Shinozaki, Hiromitu ; Tokiwa, Yoko ; 中島, 久美子 ; 伊藤, 玲子 ; 國清, 恭子 ; 荒井, 洋子 ; 阪本, 忍 ; 篠崎, 博光 ; 常盤, 洋子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />[目 的]妊娠期にある共働き夫婦を対象に,妻が満足と感じる夫の関わりにおける夫婦の認識を明らかに\nし,妻が満足と感じる夫の関わりを高める看護援助への示唆を
…
得る.[対象と方法]共働き夫婦3組を対象\nに,妻が満足と感じる夫の関わりにおける夫婦の認識ついて半構成的面接法によリデータを収集し,分析は\nベレルソンの内容分析法を参考に行った.[結 果]共働き夫婦において妻が満足と感じる夫の関わりに\nおける夫婦の認識は,[妊娠の知らせに対する喜び][仕事の継続への理解と話し合い][仕事や妊娠咄産に\n伴う心身への気づかい][家事の分担][親になるための準備]の5カテゴリーが抽出され,共働き夫婦の認識\nの共通性および差異が明らかとなった.[結 語]共働き夫婦が認識する妊娠期の妻が満足と感じる夫の\n関わりにおいて,5カテゴリーが抽出され,共働き夫婦の認識の共通性および差異が明らかとなった.妻が満\n足と感じる夫の関わりを高める看護援助として,夫婦の間で気持ちの共有と夫婦の協働的な作業や艮好なコ\nミュニケーションが強化されるように夫婦に働きかけることが重要であると示唆された.
続きを見る
|
|||
| 15.
論文 |
Imai, Mitsuko ; Tokiwa, Yoko ; 今井, 充子 ; 常盤, 洋子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />[背景・目的]本研究は,我国における行政による子育て支援と母子をとりまく社会環境に関する文献検討\nから子育て支援の視点と課題を明らかにすることを目的とした
…
.[方 法]行政による子育て支援の視点\nについては,子育て支援に関する報告書を中心に子育て支援事業に視点を当てて分析した.我国の母子をと\nりまく社会環境の変化は,医学中央雑誌を中心に「子育て」「育児」「歴史」をキーワードとして検索,分析し\nた.[結 果]行政による子育て支援に関する文献は1989~2010年の25件,母子をとりまく社会環境に関\nする文献は1945~2010年の59件が検出された.現在行政が行っている子育て支援の視点は,保育サービス\n等母親を子育てから解放することと子どもの成長に置かれていた.母子をとりまく社会環境は,現在子育て\nをしている母親は成長する過程で子育てや家庭生活に必要な能力を体得する機会,子ども及び他人との関わ\nり方を学習する機会が少ない状況にあった.また,子育てモデルをわずかしか持っておらず,夫との会話,近\n隣との交流,専門職からの生活に即した支援が少なく,子育てに試行錯誤する中で疲労や子育てに負担感を\n持ちやすいことが示唆された.[結 語]子育て支援の視点として子どもの成長を支援する視点に加えて\n母親を支援する視点を持つ必要性が示唆された.
続きを見る
|
|||
| 16.
論文 |
森島, 知子 ; 國清, 恭子 ; 堀込, 和代 ; 平川, 君恵 ; 常盤, 洋子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【背景と目的】早期産で低出生体重児を出産した母親の出産体験に関する研究は少ない. 本研究の目的は, \n早期産で低出生体重児を出産した母親の出産休験の内容を
…
明らかにし, 出産体験の意味づけへの支援を考え\nる手がかりを得ることである.【対象と方法】対象は研究実施施設で低出生体重児を出産し, 出産から1カ月検診までの間に研究参加の同意が得られた母親9名とした. データは半構成的面接法により収集した. 分析方法はベレルソンの内容分析を参考に行った.【結果】対象となった9名の出産様式は帝王切開での出産が5名, 経膣出産が4名であった. 早期産で低出生体重児を出産した母親の出産体験の内容として,【出生後の子どもの生存を憂慮した体験】,【早期産となることに恐怖を感じて出産した体験】,【危機的な状況での夫の対応に満足・不満足感を感じて出産した体験】,【医療スタッフの対応に満足・不満足感を感じて出産した体験】,【出産に伴う身体の苦痛を感じて出産した体験】,【切迫早産に伴う心身の苦痛を感じて出産した体験】の6つのコアカテゴリーが抽出された. また,【出生後の子どもの生存を憂慮した体験】,【早期産となる\nことに恐怖を感じて出産した体験】, で全記録単位数の80%を占め, この2つのコアカテゴリーが早期産で低\n出生体重児を出産した母親の出産体験の特徴を示した.【結語】本研究で抽出された出産体験の内容から, 子どもの生存を憂慮し自尊心の傷つきをもつ早期産で低出生体重児を出産した母親には, 産褥早期に妊娠中の経過からの振り返り, その時々の体験を母親がどの様に受けとめているか確認し, 意味づけを支援することが必要であると示唆された.
続きを見る
|
|||
| 17.
論文 |
中島, 久美子 ; 常盤, 洋子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />【目的】文献検討により妊娠期の妻への夫の関わりと夫婦関係を定義し,妊娠期の妻の\n精神的健康を促す夫の関わりと夫婦関係に関する研究の
…
現状と課題を明確にすることを目的と\nする。【研究方法】1988年~2008年までの論文を対象にpregnancy, transition to parenthood,\ncouple, marital relationship, support,をキーワードにして,医学中央雑誌,MedLine を中心\nに検索した。【結果】97件が検出され,妻への夫の関わりと夫婦関係に関する記述がなされ,\n学術論文の形式が整っている22論文を選んで概観した。妊娠期の妻への夫の関わりと夫婦関係\nが定義され,夫の関わりと夫婦関係に関する研究の現状および研究の課題が見出された。【結\n論】妊娠期の妻への夫の関わりと夫婦関係が定義された。また,今後の研究の課題として,以\n下2つの点が明らかにされた。①夫婦を対象とした,妊娠期の妻への夫の関わりおよび夫の親\n性の発達に影響を及ぼす夫婦関係に関する研究の必要性,②妻の精神的健康をアセスメントす\nるための夫の関わりと夫婦関係について測定可能な尺度開発の必要性が示唆された。
続きを見る
|
|||
| 18.
論文 |
荒川, 浩一 ; 常盤, 洋子
概要:
application/pdf<br />Journal Article
|
|||
| 19.
論文 |
國清, 恭子 ; 中島, 久美子 ; 阪本, 忍 ; 荒井, 洋子 ; 長岡, 由紀子 ; 常盤, 洋子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【目的】妊娠期の女性のヘルスプロモーションを支援するために, 生活圏に医療機関のない女性の妊娠期\nにおけるセルフケアの特徴を明らかにする. 【方法】沖縄県
…
の離島の黒島, 波照間島に居住する出産後1\n年以内の母親9 名を対象とし, 半構成的面接法により抽出した妊娠期に行ったセルフケアを, 質的に内容分\n析した. 【結果】離島の女性は自分の健康は自分で管理していこうという意識を持っており, 妊娠期のセ\nルフケアとして, 「妊娠経過において異常を予防し正常を保つために, 自らあらゆる情報源から情報を得て, \n自ら考え行動した」という特徴が見出された. 【結語】妊娠期の女性のセルフケア能力を高める支援とし\nて, 女性が意識的に自分の身体と向き合い自分で判断することを促すかかわり, 専門的視点からのセルフケ\nアについての振り返り, キーパーソンである夫と協働できるような支援, 個別的で具体的な情報提供という4\nつの支援が示唆された.
続きを見る
|
|||
| 20.
論文 |
常盤, 洋子 ; 國清, 恭子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【目的】文献研究により, 出産体験の自己評価に関する研究の現状と課題を明らかにし, 出産体験の自己\n評価に関する研究に有効な変数を得ることを目的とする.
…
【研究方法】1960年~2001年までの論文を対象\nに, “childbirth experience”, “self evaluation”, “scale”をキーワードにして, CINAHL, MedLine, 医学中央雑\n誌を中心に検索した. 【結果】131論文が検出され, 出産体験の自己評価について記述がなされ, 学術論\n文の形式が整っている47論文を選んで概観した. 出産体験の臨床的意義が明らかにされ, 出産体験の自己評\n価のアセスメントに有効な産科的, 心理・社会的変数が抽出された. 【結論】今後の研究の課題と方向性\nについて, 以下, 3つの視点を明らかにした. ①分娩経過の正常・異常による出産体験のとらえ方の相違を比\n較できる大きいサンプルによる調査の必要性, ②出産体験の自己評価と産後の心理的健康(例えば, 産後うつ\n傾向, 自尊感情) との関連についての実証的研究の必要性, ③出産体験の再構築と意味づけに関する実践的研\n究の必要性が示唆された.
続きを見る
|
|||
| 21.
論文 |
國清, 恭子 ; 水野, 治久 ; 渡辺, 尚 ; 常盤, 洋子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【目的】中絶を受ける女性の援助不安の実態を明らかにし, 中絶を受ける女性の心のケアのあり方を検討\nする資料を得ることを目的として調査を行った. 【対象と方
…
法】調査期間は平成15年9 月~平成16年1\n月. 15施設において中絶を受ける女性に無記名式自記式質問紙調査を実施し, 中絶前後で同一対象者によっ\nて回答が得られた100例を分析対象とした. 調査内容は, 援助不安, 被援助志向性, もらったソーシャルサ\nポート, 自尊感情であった. 【結果】医師, 看護師への呼応性, 汚名への心配が強い場合, もらったソー\nシャルサポートの量が少ないことが明らかになった. また, 「呼応性への心配」, 「汚名への心配」, 「被援助志向\n性」がもらったソーシャルサポートを規定する要因として抽出された. 【結論】中絶を受ける女性が医師\nや看護師からのサポートを受け易い状況を作り出すためには, 呼応性および汚名への心配の軽減を図るとと\nもに, 被援助志向性を高めることが必要である.
続きを見る
|
|||
| 22.
論文 |
神田, 清子 ; 牛久保, 美津子 ; 齋藤, 泰子 ; 齋藤, やよい ; 常盤, 洋子 ; 二渡, 玉江 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />群馬県内48施設で勤務する3年以上の実務経験を有する看護職751名を対象に,専門看護師に対する教育ニーズを把握する目的で,自己記述式
…
質問票を配布し調査を行った。その結果699名(回収率93.1%)から回答が得られた。専門看護師になりたい希望があるものは全体の42.5%であり,うち群馬大学に入学を希望するものは78.5%であった。専門看護師の希望分野は,がん看護が31.9%でもっとも高く,次いで地域看護,老人看護の順であった。専門看護師を希望しない理由は,「興味はあるが仕事の継続に支障をきたす心配がある」49.3%,「入試に合格するか心配である」35.6%,「大学院での教育についていけるか不安である」34.6%であった。以上,県内に勤務する看護職のニーズを参考にし,群馬県という地域性を十分にふまえた特色ある専門看護師教育カリキュラムをつくりあげ,質の高い専門看護師を実践現場に輩出していくことが本学に求められている。
続きを見る
|
|||
| 23.
論文 |
土江田, 奈留美 ; 常盤, 洋子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />【目的】不妊治療における看護のさらなる充実を図るため,先行研究の動向をレビューすることで,不妊に関する看護の研究の今後の課題について
…
明らかにすること。【方法と対象】医学中央雑誌Web版より「看護」,「不妊」のキーワードにて過去20年間にわたってわが国で発表された論文を検索した。検索された文献をテーマの趣旨にそって吟味し,それに該当した63件を対象文献とした。【結果および考察】明らかにされた今後の課題は,(1)不妊や不妊治療を体験している女性の心理状態を不安や抑うつといった概念で捉えることにとどまらず,さまざまな心現状態を想定した研究,(2)不妊を体験している女性のみでなく,夫婦・カップルの支援を考えた研究,(3)不妊について専門的な知識や技術をもった医療者によるテーム医療の体制における看護の果たす役割の明確化という3点について挙げることができた。
続きを見る
|
|||
| 24.
論文 |
常盤, 洋子 ; 松岡, 治子 ; 伊藤, まゆみ ; 神田, 清子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />【目 的】本研究の目的は,看護実践能力の育成を目指して臨池実習指導のあり方を検討する資料を得るために看護基本技術の到達度を明らかにす
…
ることである。【方 法】2000年度入学の第4期生87名を対象に臨地実習終了時の看護基本技術の経験の有無と到達度を調査し,85名から有効回答(有効回答率97.7%)が得られた。【結 果】看護基本技術の経験到達度の分析において身体侵襲を伴う処置に関する看護基本技術の経験が少なく,到達度も低いことが明らかにされた。以上のことから,臨地実習において身体侵襲を伴う処置や技術が経験できる教育環境を作る必要がある。看護基本技術の実践能力の育成にむけて以下4つの課題について検討が必要であると考えられた。(1)臨地実習指導体制の組織化,(2)身体侵襲を伴う技術教育の強化,(3)ケアの実践モデルの提示,(4)到達度評価システムの検討。
続きを見る
|
|||
| 25.
論文 |
松岡, 治子 ; 常盤, 洋子 ; 神田, 清子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,新カリキュラムにより学習した学生,本学の第5期生の臨地実習における看護基本技術の到達度を明らかにし,5期生に対する教
…
育方法の有効性を検討することである。カリキュラムの改正を行った2001年度入学の5期生76名を対象に臨地実習終了時の看護基本技術の経験度と到達度を調査し,第4期生の結果とX^2検定を用いて比較した。その結果,62名から有効回答(有効回答率81.6%)が得られた。4期生と5期生の比較では,看護基本技術80項目のうち,「経管栄養法(流動食の注入)」や「便器・尿期の使い方」などの3
続きを見る
|
|||
| 26.
論文 |
中島, 久美子 ; 土江田, 奈留美 ; 國清, 恭子 ; 常盤, 洋子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は, 母性看護学実習において, 学生が実習で体験を通して感じた内容から学習効果を抽出し, 教員の関わりを検討するための資
…
料を得ることである。母性看護学実習を行ったA大学看護学専攻4年次学生79名中, 実習初回グループをのぞく前半3グループ30名の中から, 協力が得られ実習前後で完全な回答のあった18名(60%)を分析の対象とした。二〇答法を用いた自由記述により実習前後の学生の自己概念の実態を把握した。また, 学生が「実習で感じた場面と感じたこと」について『病棟実習』, 『外来実習』, 『分娩見学実習』の3つの場所別に感じた場面を抽出し, それぞれの内容を「意味付け」して分類し, 内容の類似性からカテゴリー化を行い質的な分析を行った。分析の結果, 『病棟実習』で感じたことは「受け持ちの母親とのコミュニケーションの場面」を含む6場面に分類でき, '母親の児に対する愛情を感じる'を含む7つの「意味付け」の内容を抽出した。『外来実習』で感じたことは「妊婦健診・一ヶ月健診の場面」を含む5場面に分類でき, '妊婦は親になるという幸せな気持ちと複雑な心境でいることを知る'を含む5つの「意味付け」の内容を抽出した。『分娩見学実習』で感じたことは「出産に立ち会ったときの場面」で, '我が子の誕生は母にとって至福の喜びであると実感する'を含む5つの「意味付け」の内容を抽出した。学生が学習効果を獲得できるような教授法を展開するためには, 実習場面に適合した教員の関わりが有効であることが示唆された。
続きを見る
|
|||
| 27.
論文 |
國清, 恭子 ; 土江田, 奈留美 ; 中島, 久美子 ; 兼子, めぐみ ; 大和田, 信夫 ; 常盤, 洋子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は, 人工妊娠中絶に対し看護者が抱く葛藤を明らかにすることである。対象は, 群馬県内の総合病院2施設と個人医院1施設に勤
…
務する人工妊娠中絶の場面に関わったことのある看護者40名であった。調査方法は, 人工妊娠中絶のとらえ方に関する文章完成法テストを用いた質問紙調査であった。分析方法は, 累積KJ法を用いた内容分析を採用し, 人工妊娠中絶に関する看護者の価値観および看護観をとらえた。調査期間は2002年9月~l1月であった。その結果は, 以下の通りであった。(1)人工妊娠中絶についての葛藤には, 抵抗感と受容する気持ちがあった。(2)人工妊娠中絶を受ける女性に対しての葛藤には, 抵抗感と受容する気持ち, およびアンビバレントな感情があった。(3)人工妊娠中絶にかかわるときの葛藤には, 抵抗感と中絶を受ける女性に対し看護を提供したいという気持ちがあった。人工妊娠中絶を受ける女性により良いケアを提供するためには, 看護者自身が自己の感情を客体化し, 葛藤に対するコーピングスキルを持つとともに, 看護者相互の気持ちの理解や看護者へのサポート体制の充実を図ること, さらに, 看護者それぞれが看護観を深めていくことの必要性が示唆された。
続きを見る
|
|||
| 28.
論文 |
常盤, 洋子 ; 土江田, 奈留美 ; 渡辺, 尚
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本論文の目的は, 人工妊娠中絶前後の心理的反応と心のケアに関する先行研究のレビューを行い, 人工妊娠中絶によって妊娠を終結する女性の
…
心のケアのあり方に関する研究を概観し, 研究課題を見い出すことである。文献検索に使用されたキーワードは""abortion"", ""psychological"", ""care""であった。MEDLINE, 医学中央雑誌を中心に文献検索を行い, 過去5年間に発表された文献を選んで概観した。その結果, 人工妊娠中絶前後の心理的反応と心のケアに関する研究課題を見いだすことができた。主な研究課題として, (1)中絶前後の心理的反応と適応に関する調査, (2)人工妊娠中絶後の心のケアについて中絶前から中絶後にかけての縦断的研究, (3)人工妊娠中絶後の心のケアに関する医療現場の実態を調査, (4)ケアを実践する側の問題点の明確化をあげることができた。
続きを見る
|
|||
| 29.
論文 |
常盤, 洋子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は, 出産体験の自己評価に影響を及ぼす要因を検討し, 産む人にとって出産が価値ある体験となるような援助を工夫するための資
…
料を提供することである。本研究では, 関東地域9カ所の総合病院の産科病棟と3カ所の産院で出産した産褥1~7日目の褥婦932名を対象に質問紙調査が行われた。調査期間は, 平成12年4月~9月。調査内容は, 出産体験の自己評価尺度の短縮版(18項目, 5件法), 出産時の不安尺度(6項目, 5件法), 出産時の夫の対応に対する満足度(O-100点), 分娩現象に影響を及ぼす産科学的要因と心理的要因である。その結果は以下の通りであった。(1)出産体験の自己評価は初産婦より経産婦の方が高いことが明らかにされた。そこで, 影響要因の検討は初産婦経産婦別に行われた。(2)出産体験に影響を及ぼす産科学的要因として, 初産婦では分娩経過, 分娩時間, 分娩様式の3要因が示され, 経産婦では, 出産年齢, 分娩様式, 在胎期間の3要因が確認された。(3)出産体験に影響を及ぼす心理的要因として, 初産婦・経産婦ともに, 出産時の不安と夫の対応に対する妻の満足度が示された。(4)産科学的・心理的要因を独立変数とし出産体験の自己評価の得点を従属変数とした重回帰分析の結果, 初産婦は分娩様式, 分娩時間, 出産時の不安の3つの要因, 経産婦は出産時の不安, 分娩様式, 夫の対応に対する妻の満足度が出産体験の評価に影響を及ぼすことが明らかにされた。
続きを見る
|
|||
| 30.
論文 |
神田, 清子 ; 常盤, 洋子 ; 大野, 絢子 ; 小泉, 美佐子 ; 小板橋, 喜久代 ; 伊藤, まゆみ ; 荒川, 千秋 ; 狩野, 太郎 ; 長岡, 理恵 ; 林, かおり ; 宮本, 美佐 ; 柳, 奈津子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper
|
|||
| 31.
論文 |
常盤, 洋子 ; 杉原, 一昭
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,出産体験の自己評価と母親が抱いている理想とするお産のイメージの内容を把握し,出産体験の自己評価と母親意識の発達との関
…
係を検討することである。本研究では,出産体験についての文章完成法(以下,出産体験SCT)と理想とするお産のイメージテストを使って産後2ヶ月日の68名の母親の反応の内容分析(KJ法)を行った。その結果は,以下のとおりであった。(1)出産時の不安は,漠然とした不安,子どもの健康,分娩経過,痛みについて,前回の経験,はじめての経験,孤独への不安があげられた。(2)出産体験による成長体験として,自己成長,母になった,自分のすごさなど母親意識の発達につながるようなカテゴリーがあげられた。(3)「よいお産とは,」のイメージでは「母子の健康」に分類される回答が最も多く認められ,「安産とは,」のイメージでは「楽なお産」に分類される回答が多かった。「よいお産」のイメージは安全性,身体的産みやすさ,安心,実母への同一性,出産体験に対する満足感の5つの内容に整理された。「安産とは」のイメージは,安全で,苦痛が少ない,自然なお産を意味していた。(4)出産体験SCTと理想とするお産のイメージテストの内容分析から,出産体験の自己評価の内容と母親意識の発達との関係図が作成された。(5)関連図の解釈から出産体験自己評価と母親意識の発達との関係について5つの仮説を導き出した
続きを見る
|