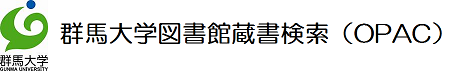※一部利用できない機能があります
| 1.
論文 |
Koike, Ayano ; Uchida, Yoko ; 小池, 彩乃 ; 内田, 陽子
概要:
Journal Article
|
|||
| 2.
論文 |
上山, 真美 ; 内田, 陽子 ; 小林, 千鶴
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,介護支援専門員をはじめとする支援者に対して行った,高齢者の排尿\nケアに関する学習会の評価と介護支援専門員が困難と感
…
じた事例の課題を明らかにすることで\nある。対象は,A地区の排尿ケアに関する学習会に参加し,協力の得られた50名とした。方法\nは,自記式質問紙法とした。結果,職種にかかわらず,約75%の者が,排尿ケアに関して困難\nと感じた課題を持っていた。学習会の内容については,約90%の者が役に立つと回答していた。\n一方,排尿日誌において学習した内容を実践してみようと思うと回答した者の得点は,役立つ\nと回答した者の得点に比べて低く有意な差がみられた(p=0.003)。また,全体で多かった課題\nは,「尿失禁の具体的ケア方法」,「受診を勧める時期」,「尿失禁のタイプ診断」であった。一方,\n介護支援専門員がその他の職種に比べて有意に高かった課題は,「オムツの種類・選択」であっ\nた。以上より,対象に合わせてオムツ選択ができるフローチャートやタイプ別排尿ケアアセス\nメント方法のフローチャートを開発し,それらを活用できるようにすることが求められる。
続きを見る
|
|||
| 3.
論文 |
上山, 真美 ; 内田, 陽子 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,自宅で生活をしている認知症高齢者の排泄行動と家族の排泄介護に影\n響する要因を明らかにすることである。対象は,A町お
…
よびB町で開催された認知症の講習会\nに参加し,調査に同意を得た48人とした。方法は,自記式質問紙法とした。結果,自宅で生活\nをする認知症高齢者は,尿とりパッドを使用しながらトイレで排泄している者が多く,家族の\n介護では,時間を見はからい声をかけている者が多かった。認知症高齢者の排泄行動や家族の\n排泄介護に影響する要因としては,以下の2点が明らかとなった。①自力での排泄行動に影響\nする認知症高齢者自身の要因は,「年齢が高い」,「認知症のレベルが重い」,「手足の不自由さ\nがある」であった。②家族の排泄介護に影響する要因は,「認知症高齢者自身に手足の不自由\nさがある」,「介護する家族の年齢が高い」であった。
続きを見る
|
|||
| 4.
論文 |
奥村, 朱美 ; 内田, 陽子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />本研究の目的は,介護老人保健施設入所中の認知症高齢者のニーズを明らかにし,ケアに必要なことを検討することである.対象は,A介護老人保健施設入所中の認知症をも
…
つ高齢者で,言語的コミュニケーションが可能なもの11名とした.方法は1対1の半構成的面接で情報を収集し,ニーズを現している言動を複数の研究者でカテゴリー化した.結果,ニーズとして,《人とつながっていたい》,《自分の生活の仕方・ペースを保ちたい》,《自分で何かやりたい》,《健康を保ちたい》,《周囲の人にはこのように自分と接して欲しい》,の5大カテゴリーが明らかになった.各ニーズの背景には介護老人保健施設入所中の認知症者の特徴がみられ,各ニーズの背景を考慮した工夫をケアに取り入れることが必要である.
続きを見る
|
|||
| 5.
論文 |
上山, 真美 ; 内田, 陽子 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,①看護学生が老年看護学実習において認知症高齢者にケアを実践した\nことによるアウトカムの変化とケア実施率,②改善がみ
…
られたアウトカム項目に対する学生の\nケア実施率を明らかにすることである。対象は,A大学4年生26名の看護学生とその受け持ち\nの認知症高齢者26名である。方法は,学生に高齢者の状態やケア内容をチェックする「認知症\nケアアウトカム評価票」の記入を,実習前後に求めた。結果,実習後のアウトカムが改善され\nた項目で多かったものは,「楽しい事に対する表現・笑顔」,「外見」,「過去の趣味・生きがいの\n実現」,「コミュニケーション」であった。この項目に対するケア実施率で高かったのは,『本\n人の好きな活動や会話を取り入れる』,『本人の過去・生い立ちの理解』,『整容を行う』,『訴え\nを聴く』などであった。反面,全体のアウトカム項目に対する『原因・背景の追究』などにつ\nいては,実施率が低かった。以上,教員は学生が高齢者のアウトカムを高められるようなケア\n実践ができるように支援していく必要がある。
続きを見る
|