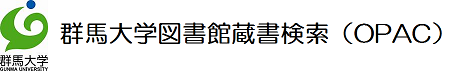※一部利用できない機能があります
| 1.
論文 |
野村, 昌史 ; 小池, 秀和 ; 松井, 博 ; 柴田, 康博 ; 羽鳥, 基明 ; 伊藤, 一人 ; 小林, 幹男 ; 鈴木, 和浩
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />群馬大学医学部附属病院泌尿器科において2007年4月より2009年3月までに, 腎腫瘍に対する体腔鏡下手術を41例に施行. そのうち70歳以上は18例, 8
…
0歳以上に限ると5例に対して体腔鏡下腎摘除術を施行した. 80歳以上と80歳未満の症例において, 手術時間, 出血量, 飲水開始時期, 食事開始時期, 術後退院までの日数について検討したところ, 飲水開始時期以外には明らかな差を認めなかった. 80歳以上の高齢者においても安全性, 侵襲の面で80歳未満症例と差がないと考えられた.
続きを見る
|
|||
| 2.
論文 |
上山, 真美 ; 内田, 陽子 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,自宅で生活をしている認知症高齢者の排泄行動と家族の排泄介護に影\n響する要因を明らかにすることである。対象は,A町お
…
よびB町で開催された認知症の講習会\nに参加し,調査に同意を得た48人とした。方法は,自記式質問紙法とした。結果,自宅で生活\nをする認知症高齢者は,尿とりパッドを使用しながらトイレで排泄している者が多く,家族の\n介護では,時間を見はからい声をかけている者が多かった。認知症高齢者の排泄行動や家族の\n排泄介護に影響する要因としては,以下の2点が明らかとなった。①自力での排泄行動に影響\nする認知症高齢者自身の要因は,「年齢が高い」,「認知症のレベルが重い」,「手足の不自由さ\nがある」であった。②家族の排泄介護に影響する要因は,「認知症高齢者自身に手足の不自由\nさがある」,「介護する家族の年齢が高い」であった。
続きを見る
|
|||
| 3.
論文 |
益田, 育子 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />本研究の目的は,通所リハビリテーションを利用する高齢者の健康管理自己効力感を探り,看護支援の方向怪を探ることである.対象者,男性36名,女性64名に調査を行
…
った.結果として,健康管理自己効力感の項目のうち,生活習慣に関する項目である「食事」「くすりの管理」「歯みがき」「体重維持」といった保健行動,「精神的安定」の平均値は高かった.平均点が低かった項目は,「健康を守るために必要な情報が集められる」「健康の維持について良い助言をしてくれる医師や看護師がみつけられる」であった.高齢者せ帯と2世代以上の世帯との比較においては,高齢者世帯の健康管理自己効力感が低かった.主観的健康感が良好な者と不良なものの比較においては,主観的健康感が不良な者の健康管理自己効力感が低かった.通所リハビリにおける看護支援では,健康を守るための情報提供や,新たな疾病や2次障害の予防などの個別・集団保健指導(相談)を積極的に行う必要があることが示唆された.
続きを見る
|
|||
| 4.
論文 |
奥村, 朱美 ; 内田, 陽子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />本研究の目的は,介護老人保健施設入所中の認知症高齢者のニーズを明らかにし,ケアに必要なことを検討することである.対象は,A介護老人保健施設入所中の認知症をも
…
つ高齢者で,言語的コミュニケーションが可能なもの11名とした.方法は1対1の半構成的面接で情報を収集し,ニーズを現している言動を複数の研究者でカテゴリー化した.結果,ニーズとして,《人とつながっていたい》,《自分の生活の仕方・ペースを保ちたい》,《自分で何かやりたい》,《健康を保ちたい》,《周囲の人にはこのように自分と接して欲しい》,の5大カテゴリーが明らかになった.各ニーズの背景には介護老人保健施設入所中の認知症者の特徴がみられ,各ニーズの背景を考慮した工夫をケアに取り入れることが必要である.
続きを見る
|
|||
| 5.
論文 |
加藤, 真理 ; 久田, 剛志 ; 石塚, 全 ; 青木, 悠 ; 柳谷, 典子 ; 解良, 恭一 ; 宇津木, 光克 ; 清水, 泰生 ; 砂長, 則明 ; 土橋, 邦生 ; 森, 昌朋 ; 桑原, 英眞
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />症例は79歳, 男性. 咳嗽, 喀痰, 全身倦怠感などを主訴に前医を受診した. 肺炎を指摘され, 前医にてセフピ\nロムの点滴静注を受けたが, 改善せず紹介
…
入院となった. 入院時採取された喀痰よりMRSA が培養され, バ\nンコマイシンなどの抗菌剤投与が行われた. しかし, 肺炎は改善せず, 人工呼吸管理を必要とし, 肝機能障害\nなども出現したため, リネゾリド投与を開始した. 2週間の投与で肺炎は著明に改善し, その後は再燃なども\nなく退院可能となった. リネゾリド投与期間中に一過性の貧血および血小板減少を認め, 赤血球輸血を必要\nとしたが, その他の副作用は認めず, 有用であった. リネゾリドは, 高齢者においても認容性に優れた有用な\n抗MRSA薬であることが示唆されたが, その使用に際しては, 薬剤耐性化などの問題も考慮した上で, 適切\nに選択していくことが必要であると思われる.
続きを見る
|
|||
| 6.
論文 |
上山, 真美 ; 内田, 陽子 ; 小泉, 美佐子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,①看護学生が老年看護学実習において認知症高齢者にケアを実践した\nことによるアウトカムの変化とケア実施率,②改善がみ
…
られたアウトカム項目に対する学生の\nケア実施率を明らかにすることである。対象は,A大学4年生26名の看護学生とその受け持ち\nの認知症高齢者26名である。方法は,学生に高齢者の状態やケア内容をチェックする「認知症\nケアアウトカム評価票」の記入を,実習前後に求めた。結果,実習後のアウトカムが改善され\nた項目で多かったものは,「楽しい事に対する表現・笑顔」,「外見」,「過去の趣味・生きがいの\n実現」,「コミュニケーション」であった。この項目に対するケア実施率で高かったのは,『本\n人の好きな活動や会話を取り入れる』,『本人の過去・生い立ちの理解』,『整容を行う』,『訴え\nを聴く』などであった。反面,全体のアウトカム項目に対する『原因・背景の追究』などにつ\nいては,実施率が低かった。以上,教員は学生が高齢者のアウトカムを高められるようなケア\n実践ができるように支援していく必要がある。
続きを見る
|
|||
| 7.
論文 |
中山, かおり 75a3df77ae63b6d85f7f5c01ec4a592c ; 臼田, 滋 ; 佐藤, 由美 ; 山田, 淳子 ; 沼田, 加代 ; 根岸, 恵子 ; 佐藤, 和子 ; 白井, 久美子 ; 齋藤, 泰子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />本研究の目的は,「第1回高齢者パワーアップ教室」と「第3回高齢者パワーアップ教\n室」における「転倒予防自己効力感尺度」「身体機能測
…
定値」「転倒リスクアセスメント」「日\n頃の仕事や家事」「運動習慣」「転倒経験」の変化を明らかにし,山間過疎地域で生活する高齢\n者の転倒予防について,支援の方向性を検討することである。研究対象は,第1回と第3回の\n両方の「高齢者パワーアップ教室」に参加した14名である。調査内容は,身体機能4項目,骨\n密度測定,転倒リスクアセスメント14項目,転倒予防自己効力感尺度10項目,仕事や家事によ\nる身体活動,運動習慣,転倒経験である。\nその結果,日頃からよく身体を動かしており,移動能力の向上が認められたが,その一方で,\n転倒予防に欠かせない調整力が低下していることが明らかとなった。また,服薬や日頃からの\nサンダルやスリッパの使用で「転倒リスクあり」の割合が高いことが明らかとなった。このこ\nとから「調整力の維持・向上につながる運動プログラムの提供」「履物や服薬等による転倒予\n防の危険性についての情報提供」を盛り込んだプログラム実施の必要性が示唆された。
続きを見る
|
|||
| 8.
論文 |
沼田, 加代 ; 根岸, 恵子 ; 平良, あゆみ ; 佐藤, 和子 ; 飯野, 理恵 ; 中山, かおり ; 佐藤, 由美 ; 齋藤, 泰子
概要:
application/pdf<br />Journal Article<br />【背景・目的】 高齢化率 (50.7%) の高い山間過疎地域において, 40歳以上の住民に健康・生活に関する調査を行った. 【対象と方法】 40~64歳は,
…
968人全住民を対象とし, 自記式質問紙調査を実施した. 65歳以上には, 1/10年齢別層化無作為抽出による156人を対象に, 聞き取り調査を実施した. 【結 果】 回答率は, 40~64歳は87%, 65歳以上は98%であった. 40~64歳の特徴として, 喫煙者は3割おり, ブリンクマン指数600以上が喫煙者の半数であった. また, 飲酒者のうち毎日の飲酒が半数であった. 肥満は3割おり, 男性の肥満の割合が高かった. 65歳以上の特徴として, 罹患率は7割であった. また, 受診や買い物は「村外」が8割であった. 将来は「今の自宅で暮らしたい」と望んでいる者は8割であった. 【結 語】 喫煙・飲酒などの嗜好品への対策, 肥満対策, 住み慣れた自宅で生活するための体制整備など成人・老年期における健康づくりや介護予防事業の重要性が示唆された.
続きを見る
|
|||
| 9.
論文 |
沼田, 加代 ; 根岸, 恵子 ; 平良, あゆみ ; 佐藤, 和子 ; 臼田, 滋 ; 佐藤, 由美 ; 中山, かおり ; 齋藤, 泰子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />【目的】山間過疎地域である群馬県N村(高齢化率51%)において,高齢者の転倒予防を検討することを目的に,転倒と関連する運動実態を明ら
…
かにする。【対象】N村MとS地区に居住する高齢者女性25名【内容】1.運動および転倒に関する状況,2.バランスおよび筋力測定,3.骨密度測定および歩数測定【結果】平均年齢は71.3±5.4歳であった。1.連動は「毎日する」が64%であり,内容は「歩く」と「体操」が多かった。転倒経験者は16%おり,転倒リスク者は24%であった。転倒予防自己効力感尺度では,「階段を下りる」と「でこぼこした地面を歩く」に「自信がない」との回答が多かった。2.バランスおよび筋力測定が,「いい状態」の割合は,片脚立位保持時間テストは56%,FRTは36%,TUGは96%,膝伸展筋力テストは4%であった。3.骨密度の健常領域は36%であった。平均歩数は7755.9±3118.9歩であった。【結論】筋力機能の低さや転倒のリスク者がいることから,地域の実情を考慮した個別の運動の推奨および転倒予防の支援の必要性が示唆された。
続きを見る
|
|||
| 10.
論文 |
佐藤, 由美 ; 沼田, 加代 ; 臼田, 滋 ; 長岡, 理恵 ; 浅川, 康吉 ; 佐光, 恵子 ; 矢島, まさえ ; 小林, 亜由美 ; 小林, 和成 ; 大野, 絢子
概要:
application/pdf<br />Departmental Bulletin Paper<br />【目的】高齢者の転倒による寝たきり防止対策を検討することを目的に, 高齢者の運動実態と運動機能との関連を明らかにする。【対象】H町K
…
地区に居住する65歳以上の高齢者35名である。【内容】内容は, 1.運動および転倒に関する状況(基本属性, 日常生活における運動の頻度・内容, 転倒の経験の有無), 2.バランスおよび筋力測定, 3.骨密度測定, 4.歩数測定【結果および考察】対象35名のうち, 男性11名, 女性24名であり, 結果は次の通りであった。日常的な運動の内容は, 「歩く」が51.7%であった。運動を「ほとんどしていない」が40.0%であった。自宅で「じっとしていることが多い」人が42.9%であった。歩数の平均値は, 男性は5983±4913歩であり, 女性は4429±2252歩であった。男女ともに加齢とともに歩数が減少する。男性よりも女性で歩数が多いほど, 筋力や骨密度が高い傾向にあった。日常生活の中で歩数を増やすための対策を検討していく必要性が示唆された。
続きを見る
|