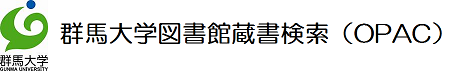※一部利用できない機能があります
特別支援学校肢体不自由部門に通学する中高等部生の障害と生活習慣の実態
- フォーマット:
- 論文
- 責任表示:
- Noda, Tomoko ; Kamata, Hisako ; 野田, 智子 ; 鎌田, 尚子
- 言語:
- 日本語
- 出版情報:
- 北関東医学会, 2012-08-01
- 著者名:
- 掲載情報:
- The Kitakanto medical journal = 北関東医学
- ISSN:
- 1343-2826


- 巻:
- 62
- 通号:
- 3
- 開始ページ:
- 261
- 終了ページ:
- 270
- バージョン:
- VoR
- 概要:
- Journal Article<br />【目的】特別支援学校肢体不自由部門に通学する中高等部生(12~17歳) の障害と生活習慣の実態を明ら\nかにし, その問題点について検討する. 【対象と方法】A 県特別支援学校肢体不自由部門4校に通学する中\n高等部生徒の保護者と担任・養護教諭を対象に質問紙調査を行い, 単純集計により分析を行った. 【結果】\n回答者数は104名であった. 起因疾患は脳神経疾患が76.9%と多く, 移動機能は寝たきりの者が49.0%, 教 … 科\n以外の教育課程の者は85.6%であった. また, 筋緊張の異常を有する者が76.9%, 脊柱側弯を有する者が73.\n1%, BMI パーセンタイルが5パーセンタイル未満の者は62.5%で, 対象児の思春期以降のQOL の向上には,\n筋緊張の亢進を緩和して脊柱側弯の進行を防止することと, 栄養管理の重要性が示唆された. 生活習慣に関\nする調査からは, 生活習慣上の問題点が3つ抽出された. 第1は「登校時間が長く, 同一姿勢で過ごすことが\n多い」で,筋緊張の亢進と脊柱側弯の進行への影響が懸念された.第2は「間食内容の不十分さ」,第3は「社\n会サービス利用の少なさ」であった. 【結語】以上から,通学用バスの収容人数を少なくし,通学時間を短\n縮するなどの対応が必要と考えられた. また, 朝昼夕の3食に間食を加えて計画的に栄養管理していくこと\nの必要性が示唆された. さらに, 卒業後の対象児と家族の生活を見通し, 学齢期から社会サービスの利用に慣\nれておくことが必要と考えられた. 続きを見る

類似資料:
|
日本肢体不自由児協会 |
金子書房 |
|
放送大学教育振興会 |
金芳堂 |
|
金子書房 |
ミネルヴァ書房 |
|
東京大学出版会 |
慶応通信 |
|
ミネルヴァ書房 |
日本肢体不自由児協会 |
|
日本肢体不自由児協会 |
日本肢体不自由児協会 |